チェンジオブコントロール(COC)条項とは?M&Aの成否を左右する重要ポイントを解説
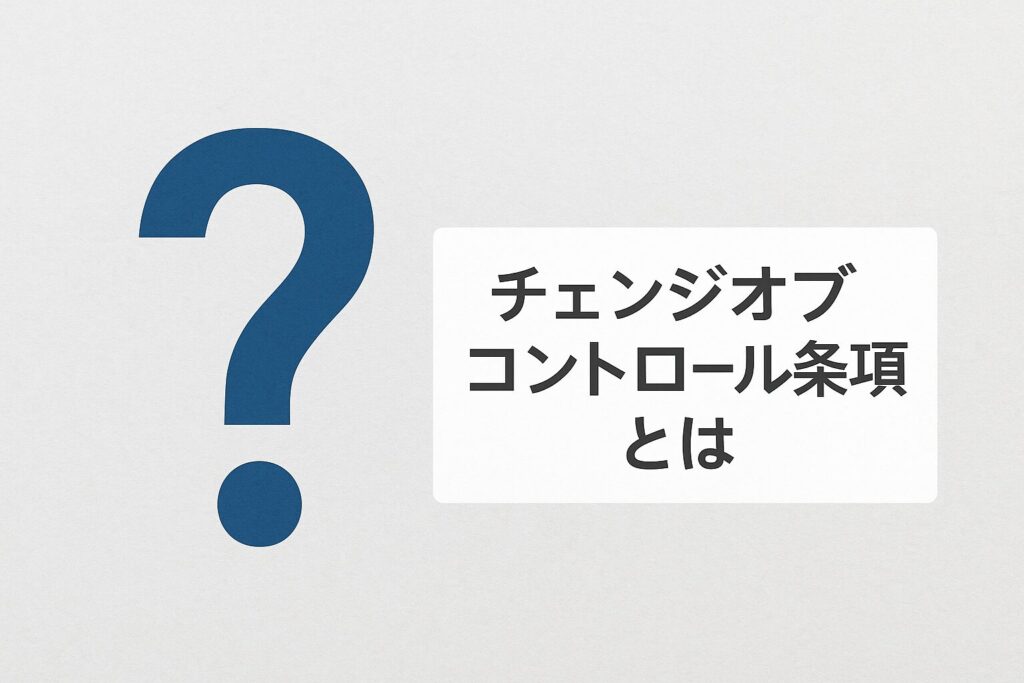
M&Aの実務において、契約書に記載されたたった1つの条項がディールの成否を左右するケースは少なくありません。その代表例が「チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control)条項」です(以下、「COC条項」とします)。COC条項への対応を誤ると、M&Aによって得られるはずだった事業価値が大きく損なわれたり、取引自体が頓挫したりする可能性もあります。
この記事では、M&Aを検討する際に避けては通れないCOC条項について、基本的な概念から実務上のリスク、COC条項が問題となりやすい契約の類型、具体的な対応策に至るまで網羅的に解説していきます。
COC条項の基本
まず、COC条項がどのようなものであり、なぜ契約に盛り込まれるのか、その基本的な仕組みから見ていきましょう。
COC条項の定義
COC条項とは、商取引に関する契約書などにおいて、契約当事者の一方に支配権(コントロール)の変更(チェンジ)があった場合に、他方当事者が何らかのアクション(契約解除など)を取れるように定めた条項を指します。
平たく言えば、「あなたの会社の経営権が他の誰かに移るなら、あなたとの契約を見直させてもらう、場合によっては契約を打ち切らせてもらう」という趣旨の取り決めです。M&Aは、まさにこの「支配権の変更」を伴う典型的な行為であるため、COC条項が実務上、重要な検討事項となるのです。
なぜCOC条項が契約に盛り込まれるのか?
企業が取引先と契約を結ぶ際、その相手方の経営状況や技術力、そして経営陣との信頼関係を評価した上で、長期的な関係を築こうとします。
しかし、将来その取引先の経営権が第三者に移ってしまった場合、契約当初の前提が崩れてしまう可能性があります。COC条項は、こうした将来起こりうる不測の事態に備え、自社を守るために盛り込まれるのです。
具体的には、以下のようなリスクを想定しています。
経営方針の変更リスク
新しい株主や経営陣の方針転換によって、それまでの良好な取引関係(価格、納期、品質など)が維持できなくなるかもしれません。
技術やノウハウの流出リスク
もし取引先の支配権を握ったのが自社の競合他社だった場合、その取引を通じて共有していた重要な技術情報や顧客情報が漏洩する危険が生じます。
コンプライアンス上の懸念
経営権を握った第三者が、反社会的勢力と関わりを持つ可能性も否定できません。
COC条項は、このような事態が発生した際に、契約を解除したり、取引条件を改めて交渉したりする機会を確保するための、いわば「自衛手段」として機能します。
【具体例】契約書の中のCOC条項
それでは、実際の契約書ではどのように記載されているのでしょうか。シンプルな例を見てみましょう。
【一般的な条文例】
第X条(支配権の変更)
|
COC条項は、定義・義務・権利に分けてチェックします。
〈定義〉何を「支配権の変更」とみなすか(例:議決権株式の過半数の移転など)。
〈義務〉支配権の変更が生じる際の、事前または事後の通知義務や、相手方の事前承諾を得る義務。
〈権利〉上記義務への違反や、承諾なき支配権の変更があった場合に、もう一方の当事者が有する権利(例:催告なしでの契約解除権)。
M&A実務でCOC条項が重要視される理由
COC条項は、単なる法務上の論点にとどまらず、M&Aの取引全体に実質的な影響を及ぼします。その主な理由は以下の3つです。
M&A取引のほとんどがCOC条項の対象
株式譲渡によるM&Aはもちろん、合併や事業譲渡など、多くのM&Aスキームは「支配権の変更」に該当します。そのため、対象会社が結んでいる契約書にCOC条項が存在すれば、そのほとんどが抵触する可能性があると考えておくべきです。
事業価値評価(バリュエーション)の前提を覆すリスク
M&Aにおける買収価格の算定(バリュエーション)は、対象会社が将来生み出すと予測されるキャッシュフローに基づいて行われるのが一般的です。この予測は、「主要な取引先との契約が今後も継続されること」を暗黙の前提としています。
もし、M&AをトリガーとするCOC条項の発動によって、売上の根幹をなす契約が解除されてしまえば、事業計画は根本から見直しを迫られます。これは、バリュエーションの前提を崩壊させ、買収価格の正当性を揺るがす事態につながりかねません。
PMI(M&A後の統合作業)への深刻な影響
M&Aは、契約を締結して完了ではありません。その後のPMI(Post Merger Integration:統合作業)が成功の鍵を握ります。
COC条項への対応が不十分なままM&Aを完了させてしまうと、PMIの段階で重要な契約が次々と解除される事態もありえます。そうなれば、期待していたシナジー効果が得られないばかりか、事業の継続そのものが困難になるかもしれません。
「支配権の変更」とは具体的に何を指すのか?
COC条項を理解する上で鍵となるのが、「何をもって支配権の変更とみなすか」という定義です。これは契約書ごとに個別に定められており、その解釈には細心の注意が必要です。
株式譲渡(過半数の取得が基本)
最も典型的なのが、株式譲渡による支配権の変更です。一般的には、以下のようなケースが該当します。
- 議決権の過半数が第三者に譲渡される場合
- 筆頭株主が変更になる場合
- 発行済株式総数の一定割合(例:3分の1、50%など)以上が譲渡される場合
単に「親会社が変わった場合」といった曖昧な表現ではなく、具体的な株式比率で定義されていることが多いのが特徴です。
事業譲渡
契約の当事者たる地位が、事業とともに譲渡先に移転する場合、契約相手から見れば「契約者が変わる」ことになるため、COC条項(または譲渡禁止条項)の対象となります。
合併・会社分割
契約の当事者たる地位が、存続会社や新設会社に包括的に承継されますが、これも実質的な支配権の変更とみなされ、COC条項が適用される場合があります。
注意すべき「間接的な支配権の変更」とは
見落としがちなのが間接的な支配権の変更です。これは、契約当事者である会社(子会社)の株主構成は変わらないものの、その親会社の株主が変わるケースを指します。
たとえば、A社(契約当事者)の親会社がB社である場合、B社の株式がC社に買収されると、A社はC社の孫会社となります。この場合、A社の直接の株主はB社のままですが、実質的な支配者はC社に変わるのです。
契約書に「直接または間接を問わず、支配権に変更があった場合」といった文言が含まれている場合、こうした間接的な変更もCOC条項のトリガーとなるため、対象会社の資本関係は注意深く調査する必要があります。
COC条項が問題となりやすい契約の類型
COC条項は様々な契約に含まれる可能性がありますが、実務上、特に注意深く確認されることが多い契約類型が存在します。
重要な業務提携契約・ライセンス契約
事業の根幹をなす技術やノウハウ、ブランドに関する契約は極めて重要です。
特に、ライセンス契約では、ライセンサー(許諾者)が、自社の技術が競合他社の手に渡ることを防ぐ目的で、厳格なCOC条項を設けていることがよくあります。
取引基本契約・代理店契約
取引基本契約や代理店契約は、売上や仕入の大部分を依存している主要な取引先との契約です。
契約相手の立場からすると、M&Aによって会社の信用力や経営方針が変わり、債権回収リスクが生じたり、取引条件が変更されたりすることを懸念します。特に、買収側が競合他社であった場合、取引の打ち切りやノウハウの流出を恐れるのは当然でしょう。
これらの契約が一つでも解除されれば、事業継続に直接的な打撃を与え、M&Aの前提であった事業価値を大きく毀損する可能性があります。
不動産賃貸借契約
本社オフィスや工場、一等地にある店舗など、代替が困難な物件の賃貸借契約において、貸主(オーナー)は、テナントの信用力や事業内容を審査して物件を貸しています。そのため、M&Aによって実質的なテナントが信用の低い会社や事業内容の異なる会社に変わることを嫌います。
COC条項によってもし不動産賃貸借契約が解除されれば、事業拠点を失うだけでなく、高額な移転コストや事業中断による逸失利益など、莫大な損害が発生しかねません。
金融機関との融資契約
金融機関が融資を行う際、その判断は対象会社の現在の経営陣、事業内容、財務状況に対する綿密な信用力審査に基づいています。M&Aによって株主や経営陣が交代すると、この審査の前提が根本から変わってしまいます。
新しい親会社の方針によっては、事業戦略が大きく変更されたり、グループ全体の財務政策の中で対象会社の位置づけが変わったりする可能性があるため、金融機関は貸倒リスクの再評価が必要と判断するでしょう。
このような理由から、借入契約にはCOC条項が含まれているのが通例です。COC条項に抵触すると「期限の利益の喪失」が発生し、借入金の一括返済を求められる可能性があります。これはM&A後の資金計画に深刻な影響を及ぼすため、極めて重要な確認項目です。
M&Aプロセスにおける実務対応の流れ
M&Aのプロセスにおいて、COC条項のリスクをどのように管理していくのか、一般的な実務の流れを解説します。
デューデリジェンス(DD)での発見と分析
M&Aの初期段階で行われるデューデリジェンス(買収監査)において、弁護士などの専門家が法務DDの一環として対象会社の全契約書を精査します。
COC条項の有無、内容、今回のM&Aで抵触する可能性を洗い出し、発見されたリスクは、契約の重要性などに応じてレベル分けされ、対応の優先順位が決定されます。
リスク発見後の具体的な対応策
DDによるリスク評価に基づき、以下の対応策を検討・実行します。
取引先からの事前同意(承諾)の取得
最も正攻法かつ確実な方法です。M&Aの実行後も契約を継続する旨の同意書を書面で取り付けます。
ただし、M&Aの情報をどのタイミングで誰に開示するかなど、慎重な判断が求められます。早すぎる開示は、情報漏洩のリスクや、万一M&Aが破談になった際の取引先との関係悪化を招く可能性があるので注意しましょう。
クロージングの前提条件への設定
M&Aの最終契約書において、「主要な取引先からCOCに関する同意を取得すること」を、取引完了の前提条件とする方法です。もし同意が得られなければM&Aを白紙撤回できるので、買い手はリスクを回避できます。
表明保証条項での手当て
売り手が「COCに抵触する重要な契約はない」と表明保証し、違反した場合に買い手の損害を補償する方法です。ただし、契約解除による事業上の損害を金銭で完全に補填することは難しいため、補助的な手段とされます。
価格調整やアーンアウトによるリスク分担
同意取得が難しい場合、そのリスク分を買収価格から減額したり、契約継続を条件に追加対価(アーンアウト)を支払ったりする方法で、リスクを買い手と売り手で分担します。
ディールブレイク(取引中止)
あらゆる手段を尽くしても、事業の根幹をなす契約の同意が得られず、リスクが許容できない場合、M&A交渉は破談、つまり「ディールブレイク」となります。
COC条項をどう乗り切るか?買い手と売り手が留意したいポイント
COC条項への対応は、法的な側面だけでなく、買い手と売り手の交渉における重要なテーマとなります。
以下では、それぞれの立場において一般的に考慮される戦略的な視点を紹介します。
買い手側が留意すべきポイント
徹底したデューデリジェンス(DD)
専門家を起用し、網羅的かつ深度のあるDDを行うことが、すべての戦略の基本となります。リスクの見落としは、後の交渉で不利な立場に陥る原因となり得ます。
キー契約の特定
数ある契約の中から、事業価値の源泉となっている「キー契約」を早期に特定し、リスク分析を集中させることが有効です。
同意取得プロセスの管理
同意取得のプロセスを売り手に任せきりにするのではなく、買い手も進捗を管理し、必要に応じて交渉の前面に出るなど、積極的に関与していくことが望ましいでしょう。
リスクヘッジの多重化
クロージングの前提条件(CP)への設定を基本としつつ、表明保証や価格調整など、複数の手段を組み合わせてリスクを最小化する戦略が求められることがあります。
売り手側が留意すべきポイント
平時からの契約管理
将来のM&Aの可能性に備え、日頃から自社が締結している契約書を整理し、COC条項の有無や内容をリスト化しておくことが理想的です。これにより、DDのプロセスが円滑に進み、買い手からの信頼も得やすくなります。
取引先との良好な関係構築
M&Aにおける交渉は、最終的に当事者間の信頼関係に影響されます。平時から取引先と良好な関係を築いておくことが、いざという時の同意取得をスムーズにするための重要な基盤となります。
誠実な情報開示
DDの段階で意図的にCOCリスクを隠蔽することは、後の表明保証違反といった深刻なトラブルに発展する可能性があります。適切なタイミングで誠実に情報を開示することが、最終的に取引を成功に導く鍵です。
まとめ
ここまで、チェンジオブコントロール(COC)条項の基本的な内容から、M&A実務における対応策まで解説してきました。
COC条項は、契約書の中では目立たない存在かもしれませんが、M&Aのプロセスにおいては、事業の価値や取引の可否に直接影響しうる重要な確認項目です。
COC条項に注意を払いながらM&Aを円滑に進めるためには、以下の点が重要です。
- デューデリジェンスによるCOC条項の早期発見
- リスクの大きさに応じた適切な対応策の検討
- 買い手と売り手の円滑な連携
- 必要に応じた専門家の活用
COC条項への対応は、法務だけでなくビジネス上の判断も求められるため、優れた知見を持つ専門家の助言が不可欠です。実際にM&Aを検討される際には、早い段階で弁護士やM&Aアドバイザーへ相談することをお勧めします。





