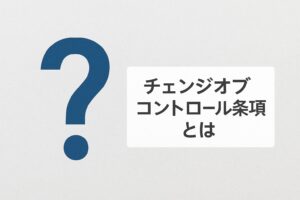M&Aと善管注意義務違反

M&Aが失敗した場合、経営判断を下した役員や取締役等が、善管注意義務違反にあたると判断されて株主から損害賠償請求を起こされることがあります。そのような事態を防ぐため、この記事では、M&Aにおいてどのような場合に取締役が善管注意義務違反を問われるのかを解説します。
取締役が負う『善管注意義務』と『忠実義務』とは
M&Aでは、取締役にさまざまな経営判断が求められます。M&A自体を行うかどうか、M&Aによってどのように企業価値を上げていくか、相手企業や売買価格など、取締役は合理的な判断を下すことが必要です。なぜなら、M&Aの成功がかかっているだけではなく、M&Aが失敗した場合に、取締役の判断が会社に損害を与えたとみなされ、善管注意義務違反を問われて損害賠償を起こされる可能性があるからです。
では、取締役が損害賠償を起こされるのは、そもそもどのような仕組みによるのでしょうか。
基本的な考え方として、取締役が「その任務を怠ったとき」に、株式会社に対して損害を賠償する責任を負います(任務懈怠責任・会社法423条1項)。
「その任務」とは法令違反などいくつかありますが、ひとつが『善管注意義務』です。株式会社と取締役は、法律的に委任関係にあります(会社法330条)。委任とは、一方の契約当事者(委任者)が相手方(受任者)に法律行為を委託することで、株式会社と取締役の場合は、会社で委任者で取締役が受任者です。
委任関係においては、受任者、つまり取締役に「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」(善管注意義務)が生じます(民法644条)。善管注意義務は、その地位に置かれた者に通常期待される程度の注意を払って業務を行う義務とされています。
善管注意義務は、委任関係に特有のものです。たとえば、雇用契約では従業員にそのような義務は発生せず、請負契約では仕事の完成が義務となります。しかし、委任契約では、取締役に専門家としての注意不足があった結果として会社に損害を与えた場合、取締役は会社に損害を賠償しなければなりません。
さらに、前述した「その任務」のひとつとして『忠実義務』があります。忠実義務とは、取締役が法令や定款、株主総会の決議を遵守して、「株式会社のため忠実に」職務を行う義務のことです(会社法355条)。
善管注意義務と忠実義務の違いですが、判例では、忠実義務は善管注意義務をさらに詳しく説明したもので別個の義務ではないと解釈されています。一方、忠実義務は取締役が会社の利益に反して自らあるいは第三者の利益を追求してはならないもので、善管注意義務と別個の義務だという考え方もあり、専門家でも意見が分かれるところです。
まとめると、取締役はその任務を怠って会社に損害を与えたときに、損害を賠償する責任を負い、対象となる任務に善管注意義務と忠実義務が含まれるということになります。
『経営判断の原則』は善管注意義務違反における判断基準
このように、取締役の経営判断には常に責任が問われますが、取締役は日々、不確かな状況下で迅速な判断を求められる場面が多く、企業利益のためには大胆な決断も時には必要です。責任を過度に問えば、取締役の業務執行が萎縮しかねません。
そのため、一定の要件において取締役に幅広い裁量を認めることで萎縮を防ぐ考え方として、『経営判断の原則』が裁判における判断基準のひとつとして確立されつつあります。経営判断の原則とは、結果的に会社に損害が生じたとしても、取締役が行う専門的な判断については、プロセスや内容に著しく不合理な点がない限り善管注意義務違反を問わないとするものです。
経営判断の原則に基づいて善管注意義務違反が否定された裁判例
とはいえ、経営判断の原則に基づいても、取締役が善管注意義務を違反したかを判断するのは困難です。前提とする事実関係が同じであっても、裁判官によって結論が異なることも少なくはありません。
たとえば、アパマンショップ株主代表訴訟では、第一審で取締役の責任を否定、控訴審ではその判決を覆し、最高裁判決ではさらにその判決を覆して取締役の責任を否定という複雑な経緯を辿っています。
アパマンショップ株主代表訴訟とは、アパマンショップホールディングスが事業再編に伴う完全子会社化のため、子会社の株式を株主から任意購入した際、株式価値の約5倍の金額で買取を行って会社に損害を与えたとして、株主が取締役に対して善管注意義務違反による損害賠償を求めたものです。具体的には、1株の価値が1万円の設定のところ、買取価格を5万円(出資価格と同じ)に設定していた点が焦点となりました。
平成22年7月5日の最高裁判決では、問題となった取引は事業再編計画の一環だったと認定し、このような事業再編計画の策定は、取締役による「経営上の専門的判断にゆだねられている」という解釈を示しています。
そして、取締役の善管注意義務について、「その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務に違反するものではないと解すべきである」との判断基準を明確にしました。
さらに、この事案の諸事情を挙げたうえで、そのような背景を考慮すれば、子会社の株式を株主から任意で購入する方法は、円滑な株式取得のためには合理性があるというべきであり、買取価格についても次の理由などから、買取価格が株式価値の5倍であったとしても「著しく不合理であるとはいい難い」と判示しています。
- 設立から5年程度しか経っていないため、出資価格と同じ5万円の価格設定は一般的にみて相応の合理性がないわけではない
- 株式は非上場株式のため評価額の幅が大きい
- 事業再編による株式価値の上昇も期待できた
この裁判例のように、取締役の責任を問う裁判では、経営判断の原則が判断基準として採用されるケースが多く、会社に損害を与えたからといって、必ずしも取締役が責任を問われるとは限りません。取締役がしかるべき注意義務を果たしたのに結果として損害が生じた場合は、基本的に責任を問われないことが多く、M&Aの裁判でも同様です。
しかし、どこまでがしかるべき注意義務か、どこまで義務を怠れば善管注意義務違反と判断されるかは、裁判での個別判断となります。そのため、M&Aで取締役が善管注意義務違反を問われないためには、経営判断に関して都度、専門家である弁護士に相談するのが望ましいです。
善管注意義務における判断基準が示された裁判例
取締役の経営判断において、どこまで善管注意義務違反が問われずに裁量権が肯定されるか、判断基準が示された裁判例を紹介します。
平成2年、そごうはトルコ共和国への出店検討のため、現地法人のA社に用地の確保などを委託、第一貸付・第二貸付と2回にわたり各1,500万米ドルずつを融資しました。第二貸付の際には、顧問弁護士や関連会社からA社の信用性や計画の実現可能性などについて疑問が呈されましたが、貸付は実行されました。
その後、湾岸戦争や出店費用の増大などの状況悪化により、そごうは平成3年に計画の静観を決定、平成5年には計画における法的問題点の調査を複数の弁護士に依頼します。しかし、そごうはA社からの債権回収を行わず、最終的に回収できたのは平成14年時点で500万円のみでした。
のちにそごうは経営破綻します。民事再生手続において、再生裁判所は取締役3名に対し、次の理由で16億2570万円の損害賠償債務を査定しました。
- 取締役は、第二貸付を中止、またはA社に対して保全措置を執るように図る注意義務があった
- 第二貸付後から平成5年までに、計画を(静観ではなく)中止し債権を回収する義務があった
この査定に対して取締役3名は意義の訴えを提起します。そして、東京地裁平成16年9月28日判決では、善管注意義務違反の判断基準を示すことで取締役の経営判断における裁量権を肯定し、査定決定を取り消して取締役の責任を否定したのです。
上記の判決をもとにすると、善管注意義務違反は、取締役の行為が次の観点において
著しく不合理であるかどうかで判断されます。
- 判断がなされた当時の会社の状況や、会社を取り巻く情勢
- 会社が属する業界において、一般的な経営者がもつ知見や経験の水準
- 判断の前提となる事実認識において、不注意がなかったか
- 事実に基づく行為の選択・決定は不合理ではないか
この事例で比較的幅広い裁量権が認められたのは、株式投資などのサイドビジネスではなく、本業についての経営判断が対象であること、会社と取締役が利益相反状況になかったことなどが理由と推察されます。
裁判などで善管注意義務違反が問われるケース
善管注意義務違反は、主に次のケースで著しい不合理があったときに問われることが多いです。
1)利益相反や法令違反
2)情報収集や調査における不合理
利益相反や法令違反
会社の利益より取締役個人の利益を優先させる利益相反や、法令違反に対しては、経営判断の原則は適用されないと判例により示されています。
情報収集や調査における不合理
取締役がM&Aなどの業務を執行する際に、情報収集や調査において著しい不合理があった場合には、善管注意義務違反を問われる可能性があります。
どの程度の情報収集や調査を行えばよいかですが、弁護士などの専門家を信頼した場合には、原則として(専門家の能力を上回ると疑われる事態を除き)善管注意義務違反を問われないとされています。また、他の取締役や使用人などからの情報を信頼した場合も、原則的には善管注意義務違反を問われません。
そのため、M&Aなどの経営判断においては、専門家に相談する、さらには専門家に相談したという履歴をつくっておくことは重要といえます。
M&Aで異業種の会社を買収し、会社に損害を与えたケース
この二つのほかにも、取締役の善管注意義務違反が問われるケースには様々なパターンが存在します。たとえば、M&Aで異業種の会社を買収したが、M&A後にその会社が倒産し、取締役が善管注意義務違反にあたるとして、株主から訴えられた裁判例です。
この事例では、次の点がポイントとなり、取締役は善管注意義務違反にはあたらないと判断されました。
- 買収した企業がベンチャー企業であったため、ベンチャー企業のM&Aにはリスクが伴う点が考慮された
- M&Aに際して、取締役がしっかり情報収集や調査を行い、経営判断を下す手続きも適正だった
このように、経営判断の過程において著しい不合理がなければ、M&Aが失敗に終わっても、取締役の責任は問われないのが原則です。そのため、M&Aの失敗で株主から訴えられる事態を避けたければ、経営判断を下すうえで適切なプロセスを踏み、訴えられるような隙をつくらないよう心がける必要があります。
M&Aで取締役の善管注意義務違反が認められた裁判例
M&Aの裁判では、経営判断の原則が判断基準として採用されるため、必要な注意義務を果たせば善管注意義務違反は問われないことが原則です。しかし、不正行為を行えば、当然ながらその限りではありません。ここでは、M&Aにおける不正行為により、取締役の善管注意義務違反が認定された裁判例を紹介します。
シャルレが、MBOのために行った株式公開買付(TOB)において、取締役は買付者であるにもかかわらず買付価格の決定に介入していました。そのことを内部通報された結果MBOが頓挫し、会社に損害を与えたとして取締役が提訴された株主代表訴訟では、取締役等が善管注意義務を違反したと認められています(大阪高裁平成27年10月29日判決)。
この判決では、取締役の善管注意義務は、最終的に「株主の利益を最大化すべき義務」に引直されると判示されました。取締役が行った不正行為により、会社が損害を受けたことで株主の利益が損なわれたため、善管注意義務に違反したと判断されたのです。
この事例では、一審で「MBO完遂尽力義務」・「手続き的公正配慮義務」といった独自の判断基準が提示されましたが、二審では否定され、善管注意義務が判断基準として採用されました。このことから、M&Aにおける不正行為をめぐる今後の裁判では、取締役に善管注意義務違反があったかどうかが焦点として問われるものと予想されます。
M&Aで善管注意義務違反を問われないためのデューデリジェンス
M&Aにおいて、取締役が善管注意義務違反を問われないよう、しかるべき注意義務を果たすためには、デューデリジェンスをしっかりと行うことが必要不可欠です。
法務デューデリジェンスの目的
デューデリジェンス(Due Diligence)とは、投資やM&Aなどの実施にあたって、対象となる会社の価値やリスクなどを調査することです。いわゆる会社調査で、主に次の分野における調査を行います。
- 事業(ビジネス)デューデリジェンス
- 財務・税務(ファイナンス)デューデリジェンス
- 法務(リーガル)デューデリジェンス
なかでも、法務デューデリジェンスは、M&Aにおいて対象企業が法的なリスクを抱えていないかを洗い出すものです。法務デューデリジェンスの目的は、調査により次の事項を判断することにあります。
1)M&A自体が実現可能か
2)売買価格は妥当か
3)M&A後に自社のビジネスプランの実現や企業価値の上昇などが実現するか
M&A自体が実現可能か
たとえば、M&Aで会社を買収し売主に代金を支払った後で、実は売主は対象企業の株主でなかったと発覚する恐ろしいケースも実際に存在します。そのため、売買自体が実現可能なのかどうか、相手会社の株主調査など基本的な調査の実施が必要です。
売買価格は妥当か
買収において、売主は会社をできるだけ高く売りたいため、価格が下がるようなマイナスの情報は隠しがちです。売主のセールストークを真に受けて、実際の企業価値とそぐわない買収価格を払った後に重大な法的リスクが判明し大損をしてしまうケースがあります。未払賃金の訴訟などの紛争トラブルや偶発債務といった法的リスクの事前調査によって、実際の企業価値に見合った買収価格を設定することができます。
M&A後に自社のビジネスプランの実現や企業価値の向上などが実現するか
たとえば、競業避止義務を負っている会社を買収してしまうと、M&A後に予定していたビジネスプランが実現できないことがあります。この場合、M&Aを行う意義がなくなってしまうので、M&A後のビジネスプラン実現や企業価値の向上を妨げるような法的リスクが存在しないかの調査が必要です。
M&Aにおける表明保証とは
デューデリジェンスを緻密に行っても、どうしても事前に発見できないリスクは存在します。このような、デューデリジェンスでは発見できないリスクがもたらす損失を補填する機能が『表明保証』です。
表明保証とは、契約の当事者(売り手)が相手方(買い手)に対して、ある時点において、提供した情報などの一定の事実が真実かつ正確であると表明・保証することです。M&Aの契約書には、表明保証条項とともに、表明保証が誤りであったときには買い手が損害賠償を請求できる補償条項を入れるのがもはや常識といえます。しかし、リスクの大きさによっては、表明保証でも補填できないほどの損害を負う可能性がある点には留意しておきましょう。
善管注意義務を問われないためのデューデリジェンス
前述したように、デューデリジェンスには目的があり、実施することでM&Aが失敗に終わる確率を極力減じることが可能です。逆に、デューデリジェンスを行わなければ、次のような法的リスクに晒される事態に陥ります。
- M&Aが無効、または撤回させられるリスク
- 法的瑕疵を見抜けず、企業価値より高額な買収金額を払ってしまうリスク
- 表明保証では補填できないほどの損害を負うリスク
このような法的リスクに気づかないままM&Aを行えば、M&Aは当然失敗に終わり、しかるべき注意義務を払わなかったとして、株主から損害賠償請求を起こされかねません。裁判で善管注意義務違反を問われないためには、適切なデューデリジェンスを専門家である弁護士に依頼することが非常に重要です。
まとめ
M&Aにおいて、取締役が善管注意義務違反を問われないためには、デューデリジェンスや取締役会における議論の実施など、取締役に通常期待される程度の注意義務を払う必要があります。このような適切な手続きを踏まない場合は、裁判で経営判断の原則に違反していると判断され、善管注意義務違反が問われる可能性が高まります。
善管注意義務違反と判断されないよう、M&Aを行う際には、専門家である弁護士に相談しましょう。前述したように、情報収集や調査において、専門家を信頼し意見を取り入れた場合には、たとえM&Aが失敗に終わっても善管注意義務違反は基本的に問われません。法務デューデリジェンスを実施し、事前に法的リスクを極力取り除くことで、M&Aを成功させましょう。