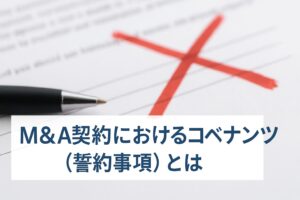M&A紛争の事例と回避策|経営者が知るべき紛争の原因やリスク・対応策を解説

M&Aは、企業を成長・存続させる戦略の一環として多くの経営者に選ばれている手法ですが、M&A紛争と呼ばれるトラブルが発生するケースも少なくありません。M&A紛争に発展すると、思い描いていたメリットが得られないばかりか、法的トラブルに発展することもあり、多大な時間・費用・労力が失われる可能性があります。
本記事では、M&A紛争がどのような状況で起こりやすいのか、実際の事例を交えながら紛争の原因や背景、予防策・対処法を解説します。
M&A紛争とは?
M&A紛争とは、M&Aに関連して生じる当事者間のトラブルや法的争いを指します。契約締結前の交渉段階から、クロージング(最終的な契約の履行)後の統合作業に至るまで、さまざまな場面で発生し得るリスクです。
中小企業庁でも、不適切な買手との間でM&A成立後にトラブルに発展した場合や、少しでも不安がある場合には、弁護士をはじめとする専門家・専門機関に相談するよう、注意を呼びかけています。
M&Aにおける紛争が発生する主な原因
本章では、M&Aにおいて特に発生しやすい紛争の原因を5つに分けて解説します。
デューデリジェンスの不備
デューデリジェンスは、M&Aの買収対象企業のリスクや実態を正確に把握するために欠かせない調査プロセスです。M&Aにおいて事前調査が不十分だと、買収後に隠れた負債や契約トラブルが露見し、買い手と売り手間での契約解除や損害賠償請求につながるおそれがあります。
例えば、M&Aの買い手企業がコスト削減を優先して調査項目を絞り込んだり、売り手の説明を鵜呑みにして調査を省略したりすると、後々重大なリスクが表面化する可能性があります。
表明保証違反
M&Aにおける表明保証とは、主に株式譲渡契約書などの締結時やクロージングにおいて、契約当事者が自社や対象会社に関する情報(例:法務・税務・財務・労務・事業内容など)が事実に基づき正確であることを相手方に対して表明し、その内容の正しさを保証するものです。
表明保証違反とは、M&A契約において売り手が「事実」として買い手に示した情報が実際には誤っていたり、欠けていたりした場合に発生する契約違反です。M&Aの買い手にとっては、事前に得た情報を前提に買収を決定しているため、その前提が崩れると、損害賠償や契約解除といった重大な法的問題に発展します。
M&Aでは、財務状況・契約関係・法的リスクなど、企業の健全性を示す多くの情報がやり取りされます。売り手はこれらについて「表明保証条項」に基づいて、正確性を保証します。しかし、実際には以下のような理由で違反が起こります。
- 隠れた債務の存在
- 裁判・係争の未報告
- 重要契約の不履行
- 環境・労働に関する問題
事前の調査や契約条項の設計をおろそかにすると、買い手・売り手ともに大きな損失を被ることになります。
表明保証条項に明らかな違反があった場合、M&A契約に基づいて損害賠償を請求されることがあります。場合によっては、契約自体が解除される可能性もあります。M&Aの売り手・買い手ともに多大な時間・労力・資金を投じている中で契約が白紙に戻ることは、大きな損失につながります。
損害賠償請求については、表明保証で記載された内容が事実と異なっていた場合、たとえ故意や過失がなくても、M&Aの買い手が被った経済的損害について賠償を求められる可能性があります。
秘密保持や競業避止義務の違反
M&Aの実施後、売主が競合他社を立ち上げたり、売却先の機密情報を持ち出して使用したりした場合、買収側に大きな損失を与えます。こうした行為は「競業避止義務」や「秘密保持義務」に反する行為としてM&A契約違反とされ、法的措置や損害賠償請求の対象となります。
こうしたM&A契約違反は、売却先のビジネスモデルや成長戦略に直接的なダメージを与えるため、買収側にとっては極めて重大な問題です。
対価の調整・支払トラブル
M&Aにおける対価の支払いは、企業間の信頼と契約の根幹をなす部分です。とくに「アーンアウト条項(業績連動型の後払い)」や「簿外債務の存在」「運転資本の調整」などは、解釈や数値算出の違いで紛争になりやすい項目です。
M&Aの買収対価には、以下のような要素が含まれることが一般的です。
- 対価調整の項目:紛争の主な原因例
- 運転資本の調整:引渡し時の資産・負債の水準が合意条件と異なる
- アーンアウト:売却後の業績未達で支払い拒否、あるいは基準の解釈の相違
- 簿外債務の発見:デューデリジェンスで見逃されていた負債により後から損害発生
- 税金・退職給付引当金:簿価との差異によって、実質的な純資産が減少
数値や評価基準に関する不一致が後から判明し、買収価格が「高すぎた」「騙された」と感じた買い手が、売り手に損害賠償を請求するケースも少なくありません。
PMI(統合プロセス)の失敗
PMIとは、M&Aによる買収後に異なる企業文化・組織・制度などを円滑に統合していくプロセスのことです。買収契約が完了したからといって、統合がスムーズに進むとは限りません。準備不足や対応の遅れは、従業員の離反や目標未達などの深刻なトラブルを招きます。
PMIでは、例えば次のような調整や意思疎通が求められます。
- 組織体制の再編成:重複部署の整理、役職・権限の調整
- 人事制度:給与体系、評価制度、福利厚生の統一
- 企業文化の融合:意思決定のスピード、仕事の進め方、価値観の違い
- 情報システム:業務フローやITインフラの整合性
- ブランド・事業戦略:製品名やサービスの統一、市場ポジションの整理
こうした統合を軽視してしまうと、従業員の混乱や不満が蓄積し、人材流出や内部対立を引き起こすおそれがあります。
M&A紛争を未然に防ぐための回避策
M&Aは企業の成長や事業承継に有効な手段ですが、契約内容や手続きに不備があると、思わぬ「紛争」に発展するおそれがあります。M&Aを成功させるには、トラブルの芽を事前に摘む「回避策」を講じておくことが極めて重要です。
本章では、M&A紛争を防ぐための代表的な回避策を4つ紹介します。
デューデリジェンスの徹底
M&A紛争の回避には、事前の「デューデリジェンス」を徹底することが重要です。
なぜなら、多くのM&A紛争は事前調査が不十分なまま進められ、後になって予期せぬ債務や隠れたリスクが発覚することに起因しているためです。
デューデリジェンスを徹底すべき主な項目としては、次のようなものがあります。
| 項目 | 主な調査内容 | 主な目的 |
| 財務デューデリジェンス | 財務諸表、負債状況 | 隠れた債務の把握 |
| 法務デューデリジェンス | 契約内容、訴訟の有無 | 法的リスクの特定 |
| ビジネスデューデリジェンス | 市場環境、競合状況 | 収益性や将来性の評価 |
| 人事デューデリジェンス | 人材構成、労務問題の有無 | 買収後の組織運営の円滑化 |
専門家や外部の第三者機関を活用し、自社だけでは気付きにくいリスクを客観的に評価することも大切です。このようにデューデリジェンスを徹底的に実施することで、後々発生する可能性のあるM&A紛争を最小限に抑えられます。
契約条項の見直し
M&A紛争を未然に防ぐには、契約書に定める条項を細部まで見直すことが重要です。
なぜなら、多くのM&A紛争は、契約書に記載された表現や認識の相違、解釈の違いから発生するからです。契約書の記載が曖昧だと、買収後に予期せぬ問題が表面化し、大きな紛争に発展することがあります。
M&Aの契約条項の見直しは、次のような項目に特に注意して進めることが大切です。
| 項目 | 主な調査内容 | 主な目的 |
| 表明保証条項 | 資産、負債、法的問題等の正確な記載 | 後からの認識違いや債務発覚を防ぐ |
| 対価の調整条項 | 売買代金の支払い方法・時期の明確化 | 支払い時のトラブルを防ぐ |
| 競業避止条項 | 譲渡後の競合事業の禁止範囲の明確化 | 買収企業との競合トラブルを防ぐ |
| 秘密保持条項 | 情報開示の範囲・守秘義務の明確化 | 情報漏洩によるリスクを回避する |
このように契約条項を入念に見直し、曖昧さや解釈の余地を減らすことで、M&A紛争のリスクを大幅に軽減できます。
表明保証事項を見直す際のポイント
表明保証条項の内容を見直す際には、M&Aの売り手と買い手の立場で関心の方向性が大きく異なります。M&Aの売り手にとっては、損害賠償や契約解除といったリスクをできる限り回避したいため、表明保証の項目数を抑えたいと考えるのが一般的です。一方、M&Aの買い手側は、将来的な損失リスクを防ぐために、表明保証条項をより広範かつ詳細に求める傾向があります。
こうした立場の違いを踏まえて、売り手が注意すべき点の一つは「明確な情報開示」です。表明保証に関するトラブルは訴訟に発展するケースも多く、曖昧な表現や解釈に幅がある文言が記載されていると、意図とは異なる解釈がされ、予期せぬ損害賠償責任が生じるリスクがあります。したがって、情報は正確かつ明確に記載することが重要です。
また、当然ながら虚偽の申告は厳禁です。不利な情報であっても隠すことなく開示し、正しく契約書に反映させることで、後のトラブルを防ぎ、不要な損失を回避することができます。誠実な対応が、M&Aを成功に導く鍵となります。
一方で、M&Aにおける買い手側にとっては、前述したデューデリジェンスの徹底が極めて重要です。十分な調査を行わなければ、M&Aの売り手があえて開示していない不都合な情報やリスクが見過ごされる可能性があります。これらの情報を見落とすと、契約締結後に予期せぬトラブルが発生し、損害を被る恐れもあります。
そのため、取引を円滑に進める上でも、将来的なリスクを回避する上でも、M&Aの対象企業の財務・法務・税務・労務などあらゆる側面において、慎重かつ丁寧にデューデリジェンスを実施することが不可欠です。
PMIの適切な管理
M&A紛争を回避するためには、PMIの適切な管理も重要です。なぜなら、PMIがうまくいかないことが、買収後の期待値とのギャップや従業員の離職、業績悪化といったトラブルを引き起こし、紛争に発展する可能性が高いためです。
特に以下のポイントを意識してPMIを適切に管理することが、M&A紛争の回避につながります。
| 項目 | 具体的な内容 | 目的 |
| 明確な統合計画の策定 | 統合後の組織構造や人員配置、業務プロセスを明確化する | 買収側と被買収側の認識のズレを防ぐ |
| 定期的なコミュニケーション | 経営陣同士、従業員間で定期的な情報共有を行う | 不安や不信感を取り除き、組織の一体化を促進する |
| 組織文化の統合 | 異なる企業文化を尊重しつつ、共通の価値観を作り上げる | 従業員の離職を防ぎ、組織の安定性を高める |
適切なPMI管理を実施すれば、M&A後のトラブルを未然に防ぎ、企業統合の成功につなげることが可能です。
専門家の活用|弁護士・M&Aアドバイザーの役割
M&A紛争の発生リスクを抑えるには、弁護士やM&Aアドバイザーといった専門家の活用が非常に効果的です。なぜなら、M&Aに関する契約内容やデューデリジェンス、PMIなどは専門的な知識と豊富な経験が必要であり、企業単独では見落としや誤解によるトラブルが発生しやすいためです。
以下に、弁護士とM&Aアドバイザーの主な役割をまとめました。
| 主な役割 | 活用するメリット | |
| 弁護士 | ・M&A契約書の作成・審査
・M&Aに関する法的リスクの洗い出し ・法務デューデリジェンスの実施 ・M&A紛争時の交渉・調停支援 |
・法的リスクの未然防止
・紛争発生時の迅速な対応 |
| M&Aアドバイザー | ・企業評価(バリュエーション)
・デューデリジェンスの支援 ・PMI計画の策定支援 |
・価格や条件面の公平性確保
・統合後の円滑な経営運営 |
専門家の支援を受けずにM&Aを進めると、法的リスクや財務リスクを見落としてしまうおそれがあり、結果的に大きな紛争を招く可能性があります。一方、専門家の知見を活用することでリスク管理を強化でき、安心してM&Aを進めることが可能です。
M&A紛争が発生した場合の対応策
M&A紛争が起きてしまった場合には、冷静かつ迅速な対応が重要です。なぜなら、対応を誤ると問題がさらに複雑化し、経営への影響が拡大してしまうおそれがあるためです。紛争が長期化すれば経営資源が無駄になり、企業イメージの低下にもつながります。
本章では、M&A紛争が発生した場合の効果的な対応策を解説します。
交渉による解決方法|訴訟を避けるための戦略
M&A紛争が起きた際には、まず訴訟を避けるために「交渉による解決」を目指すことが重要です。
なぜなら、訴訟は多額の費用や時間がかかり、さらに企業間の関係悪化を招く恐れがあるためです。紛争を早期かつ円満に収束させることが、双方の企業にとって望ましい選択です。
交渉でM&A紛争の解決を図る際は、以下の3つの戦略を意識しましょう。
| 戦略 | 具体的な方法 | ポイント |
| 早期対話の開始 | 紛争が小さい段階から相手企業と対話を持ち、互いの主張を整理する | 初動が早ければ紛争が拡大しにくい |
| 客観的資料の活用 | デューデリジェンスや契約書などの書面をもとに、冷静かつ客観的に話し合う | 主観的・感情的な対立を防ぐ |
| 第三者専門家の仲介 | 弁護士やM&Aアドバイザーなどの専門家を交渉の場に同席させ、公平な立場からの助言を受ける | 話し合いの公平性を担保しやすい |
特に第三者専門家の活用は効果的です。紛争当事者同士だけの話し合いは感情的になりやすく、解決が難しくなることが多いため、専門家を交えることで交渉がスムーズに進みます。
M&A紛争では訴訟を回避し、企業価値を損なわないよう「早期に交渉の場を設け、客観的な資料を用いて専門家とともに解決を図る」という戦略を徹底することが大切です。
弁護士を立てた上での交渉協議
M&A紛争が発生した場合は、速やかに弁護士を立てて交渉協議を進めるのが最善策です。なぜなら、M&A紛争は専門性が高く、法律知識や経験が豊富な弁護士の助言がなければ、不利な条件で合意を強いられる可能性があるためです。
感情的になりやすい当事者間での直接交渉だけでは、M&A紛争の解決が困難になることも珍しくありません。M&A紛争の発生にあたって、弁護士を立てることで得られるメリットは、主に以下のとおりです。
- 冷静かつ客観的な対応が可能
- 専門的知識をもとに有利な交渉が可能
- 法的リスクを事前に把握し、訴訟を避けた円満な解決へと導ける
弁護士が交渉協議に参加することで、専門的な見地から主張の根拠を明確に示し、スムーズな紛争解決を可能にします。結果として、企業価値を大きく損なう長期的な訴訟や紛争の拡大を防ぐことにつながります。
M&A紛争が起きた際は、速やかに弁護士を立てて交渉に臨むことが、最も合理的かつ効果的な選択です。
訴訟手続き|法的措置を取る際のポイント
M&A紛争が交渉だけで解決できない場合、訴訟手続きを取ることも視野に入れる必要があります。なぜなら、相手側が交渉に応じない、または条件面で著しく不利な提案を提示している場合には、裁判所を通じて紛争解決を図るほうが結果的に有利になる可能性があるためです。
以下に、M&A紛争に対して訴訟手続きを検討する際に注意すべきポイントを示しました。
| 注意点 | 詳細 |
| 証拠資料の整備 | 契約書類、メール、議事録、財務諸表など、紛争の原因を証明できる資料を漏れなく整理し準備する |
| 弁護士の早期起用 | 弁護士を早めに起用し、訴訟戦略を練ったうえで、勝訴可能性やリスクを客観的に評価してもらう |
| 経営への影響を検討 | 訴訟が長期化した場合の経営面への影響(時間的・経済的コスト、ブランドへのダメージ)を事前に考慮し、訴訟を続けるべきか和解に転じるべきかの判断を適時行う |
訴訟は、相手との関係を決定的に悪化させる可能性があります。そのため、法的措置を取るかどうかを判断する際には、感情論を排除し、ビジネス上の合理的な視点で意思決定することが求められます。
万が一、訴訟に至った場合は、迅速な対応と適切な専門家の起用により、自社の権利を守り、被害を最小限に抑えましょう。
M&A後のリスク管理|将来的な紛争を防ぐためにできること
M&A紛争が発生した後も、将来的な紛争を未然に防ぐためのリスク管理を継続して行うことが重要です。一度M&A紛争が生じた企業間では、小さな誤解や情報不足でも新たなトラブルへと発展する可能性があります。
以下に、M&A後にリスクを管理し、将来的な紛争を防止するための主なポイントをまとめました。
| リスク管理のポイント | 詳細 |
| 定期的なコミュニケーション | 定期的な会議や情報交換の場を設け、経営方針や財務状況などを共有し誤解を防ぐ |
| 明確な役割分担と意思決定プロセスの整備 | PMIを確実に進めるため、両社の役割や責任を明文化し、意思決定方法を明確にする |
| 継続的なデューデリジェンスの実施 | 定期的な財務・法務監査を行い、問題を早期に発見して対処する |
M&A紛争の具体的な事例
具体的な事例を知っておくことが、M&A紛争を未然に防ぐための重要な第一歩となります。本章では、よく見られる代表的なM&A紛争の事例を紹介します。
価格調整をめぐる紛争|買収後に発覚する財務リスク
M&A紛争の中でも、価格調整をめぐる紛争は多く発生しています。価格調整とは、M&Aによる買収時に提示された企業価値と、M&Aによる買収後に発覚した実際の企業価値とのギャップを埋めるための仕組みです。M&Aでは契約成立後に、簿外債務や未計上の負債が明らかになるケースが少なくないため、価格調整が行われることがあります。
以下に、価格調整に関するM&A紛争の事例と原因を示しました。
| M&A紛争の事例 | 発覚した財務リスク | M&A紛争が起きた原因 |
| 簿外債務の発覚によるトラブル | 買収後に約3億円規模の債務が発覚した | 売り手側の会計処理が不適切だった |
| 売掛金回収不能リスク | 売掛金約1億円が実質回収不能だったことが判明した | デューデリジェンス時の資産評価が不十分だった |
| 在庫の過剰評価 | 買収後に在庫評価額が実際より大幅に高く見積もられていたことが判明し、資産が数千万円規模で過大評価されていた | 売り手側が意図的に在庫を高く評価した |
買収後に予想外の財務リスクが発覚すると、買い手側の経営計画に大きな狂いが生じ、追加資金の投入や経営の混乱を引き起こすことになります。そのため、価格調整をめぐって、売り手側との紛争が発生しやすくなるのです。
価格調整条項を明確に定めることと、徹底したデューデリジェンスの実施が、財務リスクに起因するM&A紛争を防ぐために不可欠な対応策です。
契約不履行による紛争|表明保証違反の事例
M&A紛争の中でも、「契約不履行」による紛争は特に多く、その代表的なものとして「表明保証違反」が挙げられます。
以下に、表明保証違反がもたらしたM&A紛争の事例をまとめました。
| M&A紛争の事例 | 詳細 | 違反内容 |
| 訴訟リスクの隠蔽 | 買収後、売り手が重大な訴訟リスクを隠していたことが発覚し、多額の損害賠償を求める紛争に発展した | 法的リスクに関する情報開示の不備 |
| 財務情報の不正確さ | 買収対象企業の財務情報に粉飾決算があり、実際の業績が著しく悪かったため、買収価格が適切でないとして紛争に至った | 財務状況に関する虚偽の保証 |
| 許認可取得状況の虚偽申告 | 事業継続に必要な行政許認可が取得されていなかったことが買収後に発覚し、事業運営が困難となった | 許認可の状況に関する虚偽の表明 |
表明保証違反によるM&A紛争を防ぐためには、契約前に徹底したデューデリジェンスを行うとともに、契約書においても、違反があった場合の責任範囲や損害賠償の条件を明確に定めておくことが大切です。
従業員や取引先との摩擦|M&A後の統合プロセスで生じる問題
M&A後のPMIにおいて、「従業員や取引先との摩擦」は紛争につながりやすい重要な問題です。PMIが円滑に進まないと、当初の期待通りの成果が出ず、経営上の深刻な問題に発展します。
従業員や取引先との摩擦による紛争の事例として、ある製造業において、M&A後に買収先企業の従業員への十分な説明やケアが不足したため、大量退職が発生しました。その結果、製品品質の維持が困難になり、顧客から多額の損害賠償を請求される事態にまで至りました。
また、別の事例として、統合後に取引条件の見直しを強行した結果、有力な取引先が離反し、売上が大幅に減少したケースもあります。
こうしたM&A紛争を防ぐには、PMIの段階から従業員や取引先への丁寧な説明やコミュニケーションに取り組むことが重要です。経営陣が早期に課題を洗い出し、適切な配慮を行うことで摩擦を回避し、円滑な統合につながります。
経営方針の対立|株式譲渡後に発生する経営権争い
経営方針の対立も、M&A紛争として頻繁に見られるトラブルです。特に株式譲渡によって買収した後は、旧経営陣と新経営陣の間で経営権をめぐる紛争が発生しやすくなります。
例えば、あるIT企業がM&Aを行った際、新たな経営陣が「利益率の高い事業への集中」を方針として掲げました。しかし旧経営陣は、従来型の広範な事業ポートフォリオを維持する方針を強く主張しました。この経営ビジョンの食い違いが社内での混乱を生み、両者間の対立が法的紛争へと発展しました。
また、株式譲渡契約の際に経営権の取り決めが曖昧だったため、買収後に双方が自らの権利を主張し合い、企業運営が停滞してしまったケースもあります。
M&A後の経営権をめぐる対立を防ぐには、株式譲渡契約時に明確に経営権や役員人事に関する取り決めを交わすことが不可欠です。さらに、事前に経営ビジョンのすり合わせを入念に行い、契約内容に落とし込むことで、譲渡後の経営方針の対立を未然に防ぐことが可能です。
M&A紛争の事例と回避策まとめ
M&A紛争は、一度発生すると企業の成長を阻害する大きなリスクになります。そのため、経営者は事前に十分なリスク管理を行い、紛争の未然防止に努めることが大切です。
M&A紛争の発生および深刻化を防ぐ対策として、以下のような施策を検討することをおすすめします。
- 徹底したデューデリジェンスを行う
- 契約内容を明確に規定し、表明保証条項などの詳細を詰める
- 買収後のPMIを慎重に管理する
- 弁護士などM&A専門家と連携し、交渉段階からリスクを洗い出す