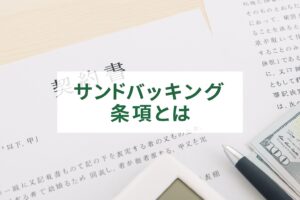さくら薬局グループの例に見る過剰なM&Aと経営破綻の危険性
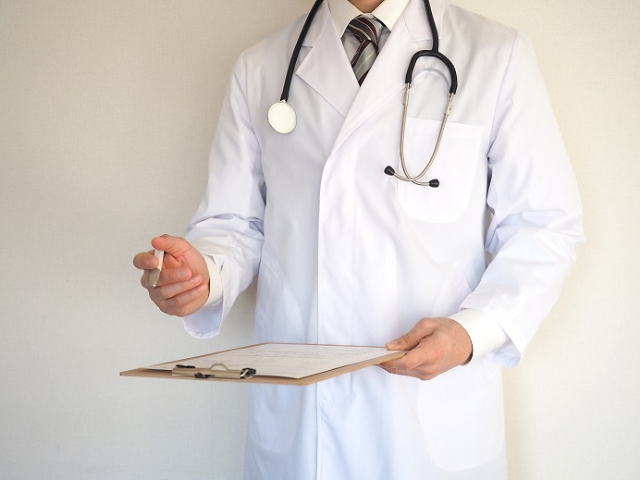
調剤薬局のM&Aが盛んになった背景
調剤薬局のM&Aは20年以上前から盛んに行われるようになっています。
さくら薬局グループがM&Aに積極的に取り組んだのも、その時代の流れに沿ったものでした。
結果として破綻してしまいましたが、本来ならば調剤薬局のM&Aは経営にとって効果的な手段です。
そこで、まず調剤薬局がM&Aを実行する理由や背景について簡単に検討しておきましょう。
調剤薬局がM&Aをする背景やメリットについては、次のような事柄が考えられます。
- 薬剤師の確保
- 立地の確保
- 調剤報酬改定の影響
以下でそれぞれについて解説します。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
薬剤師の確保
調剤薬局に必要な薬剤師の人数は法定されています。
「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」では、1日平均取扱処方箋数を40で除して得た数、すなわち、処方箋40枚につき1人の薬剤師を設置することが定められています。
このため、調剤薬局の収入源の大部分を占める調剤報酬を増やすためには、薬剤師をより多く確保する必要があります。
一方で、薬剤師の数は慢性的に不足しています。
調剤薬局の数は年々増加しているにも関わらず、2006年からは薬学部が6年制に移行したこともあって薬剤師の数は足りず、人員の確保が難しい状況にあります。
一般的に大手企業の方が就職先として好まれる傾向がありますので、薬剤師を確保するためには大規模チェーンの方が有利です。
このような事情から、薬剤師を確保するために調剤薬局チェーンの大規模化が推進されています。
立地の確保
2015年に内閣府が公表した「医薬分業における規制の見直し」という資料では、医療機関で処方箋を受け取った後どこの薬局に行くかというアンケートに対し、69.1%もの方が「医療機関からなるべく近い薬局」と答えています。
このアンケート結果からは、医療機関に近い立地を確保することができればそれだけ多くの来客が見込めるため、店舗の立地が非常に重要になっています。
実際にも、病院や医院などの医療機関の近隣にはほとんどの場合で薬局が存在します。
このような薬局は門前薬局とも言われますが、この門前薬局をM&Aで取得できれば、医療機関の利用者を独占することができるため経営にとって大きなプラスとなります。
調剤報酬改定の影響
調剤薬局の収入に大きく関係する調剤報酬は、原則として2年毎に改定されます。
増大する医療費は国の財政赤字に大きな悪影響を与えているため、国は医療費の削減に取り組んでおり、薬価はマイナスに改定される傾向にあります。
一方で、かかりつけ薬剤師指導料のように加算される項目が新設される場合もあります。
これは、かかりつけ薬剤師になるとかかりつけ薬剤師指導料が加算されるという制度ですが、24時間対応が求められるため薬局は24時間営業ができる体制を整える必要がありました。
薬剤師の確保とも関係しますが、営業体制を強化して調剤報酬を増やす観点からもグループの規模を大きくすることが求められており、M&Aで規模を拡大する必要性があります。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
さくら薬局グループの拡大路線
さくら薬局グループは盛んにM&Aに取り組んで規模を拡大してきました。
しかし、M&Aを積極的に行ったのはさくら薬局グループだけではありません。
他の調剤薬局グループも、同様に中小の調剤薬局を取得して店舗数を増やしています。
調剤薬局業界では全体としてM&Aがよく行われていますので、ここではさくら薬局グループと他の調剤薬局グループのM&A事例について検討します。
さくら薬局グループのM&A推移
さくら薬局グループのM&Aを中心とした沿革の主要部分は次のようになっています。
| 1982年10月 | クラフトファーマシー株式会社を設立 |
| 1983年1月 | 東京都板橋区に調剤薬局の板橋1号店が開設される |
| 1988年6月 | クラフト株式会社に商号変更 |
| 2004年12月 | ジャスダックに上場 |
| 2005年3月 | 株式会社サンメディックから営業の全部譲受 |
| 2005年11月 | 東京調剤株式会社を子会社化 |
| 2006年11月 | 有限会社平成調剤から営業の全部譲受 |
| 2008年4月 | MBOを行い上場廃止 |
| 2020年 | グループ全体で1000店舗超になる |
| 2022年4月 | 経営難となり事業再生ADRを申請する |
| 2023年3月 | 日本産業推進機構グループ(NSSK)に株式を譲渡 |
| 年 | 店舗数 |
| 2006年 | 218 |
| 2007年 | 245 |
| 2008年 | 270 |
| 2020年 | 1002 |
さくら薬局グループを展開するクラフト株式会社は、2004年12月にジャスダックに上場しましたが、2008年4月に上場を廃止しています。
上場廃止後には詳細な情報が公表されていませんが、限られた公開情報からは急速な店舗数の増加が見て取れます。
1983年に初めての店舗を開設してから20年以上を費やして2006年に218店舗となりましたが、そこから2008年までの2年でM&Aによる取得も含めて52店舗を増やしています。
また、さくら薬局グループは2008年の上場廃止後にもさらに積極的にM&Aを続け、2008年から2020年までの12年間で700店舗以上を増やす急拡大を行い、1000店舗を超えるまでに成長しました。
これは、単純平均すると1年あたり約60店舗が増加した計算になります。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
アイングループの場合
業界最大手であるアイングループの主要な沿革は次のようになっています。
| 1969年8月 | 前身となる株式会社第一臨床検査センターを設立 |
| 1993年5月 | 旭川市に処方箋保険調剤薬局を開局 |
| 1998年11月 | 株式会社アインファーマシーズに商号変更 |
| 2002年11月 | 今川薬品株式会社(44店舗)を吸収合併 |
| 2004年5月 | ナイスドラッグ株式会社(10店舗)を子会社化 |
| 2005年4月 | 株式会社リジョイス及び株式会社リジョイス薬局(合計16店舗)を子会社化 |
| 2006年4月 | 株式会社ダムファールマ及びメディカルハートランド株式会社(合計17店舗)を子会社化 |
| 2007年1月 | 株式会社ダイチク(18店舗)を子会社化 |
| 2007年6月 | 株式会社あさひ調剤(86店舗)を子会社化 |
| 2007年11月 | サンウッド株式会社(5店舗)を子会社化 |
| 2009年4月 | 東証2部に上場 |
| 2010年4月 | 東証1部に上場 |
| 2015年2月 | 株式会社メディオ薬局(52店舗)を子会社化 |
| 2015年11月 | NPホールディングス株式会社(41店舗)を子会社化 |
| 2015年11月 | 株式会社アインホールディングスに商号変更 |
| 2016年12月 | 株式会社葵調剤(115店舗)を子会社化 |
| 2018年9月 | 株式会社コム・メディカル及び有限会社ABCファーマシー(合計56店舗)を子会社化 |
| 2019年3月 | 土屋薬品株式会社(36店舗)を子会社化 |
| 年 | 店舗数 |
| 2006年 | 218 |
| 2008年 | 356 |
| 2010年 | 397 |
| 2015年 | 754 |
| 2020年 | 1088 |
| 2023年 | 1209 |
アイングループもM&Aを積極的に行って店舗数を増やしています。
2006年には218店舗だったのが、2020年には1088店舗を数えるまでになり、さくら薬局グループと同様の増加数を示しています。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
クオールグループの場合
業界3位のクオールグループの主要な沿革は次のとおりです。
| 1992年10月 | クオール株式会社設立 |
| 2001年3月 | 株式会社スズハを子会社化 |
| 2001年9月 | 有限会社サワダに資本参加し子会社化 |
| 2001年11月 | 株式会社スズハから5店舗の営業譲受 |
| 2001年12月 | 株式会社スズハ(7店舗)を吸収合併 |
| 2002年6月 | 株式会社サンステップを子会社化 |
| 2003年1月 | 株式会社光栄ファルマを子会社化 |
| 2006年4月 | 大阪証券取引所(現 ジャスダック)に上場 |
| 2006年10月 | 株式会社福聚(9店舗)を子会社化 |
| 2007年3月 | 株式会社ビー・エム・エルから6店舗の営業譲受 |
| 2007年7月 | 株式会社メディカルコムから4店舗の営業譲受 |
| 2007年10月 | 株式会社エーベル(64店舗)を吸収合併 |
| 2008年7月 | 株式会社イムノファーマシー大阪(24店舗)を子会社化 |
| 2010年2月 | テイオーファーマシー株式会社(21店舗)及びテイオードラッグ株式会社(4店舗)を子会社化 |
| 2011年12月 | 東証2部に上場 |
| 2012年12月 | 東証1部に上場 |
| 2012年12月 | 株式会社レークメディカル(17店舗)を子会社化 |
| 2013年4月 | 株式会社アルファーム(23店舗)を子会社化 |
| 2014年3月 | 株式会社セントフォローカンパニー(33店舗)を子会社化 |
| 2016年10月 | 株式会社共栄堂(86店舗)を子会社化 |
| 2018年10月 | クオールホールディングス株式会社に商号変更 |
| 2019年8月 | 株式会社セラ・メディック(10店舗)を子会社化 |
| 2021年1月 | 株式会社勝原薬局(11店舗)を子会社化 |
| 2021年7月 | 有限会社ケーアイ調剤薬局(8店舗)を子会社化 |
| 2022年11月 | 北摂調剤株式会社(8店舗)を子会社化 |
| 2023年1月 | 株式会社パワーファーマシー(38店舗)を子会社化 |
| 年 | 店舗数 |
| 2006年 | 105 |
| 2008年 | 198 |
| 2010年 | 269 |
| 2015年 | 536 |
| 2020年 | 805 |
| 2023年 | 892 |
クオールグループもM&Aを頻繁に行うことで店舗数を増やしています。
特に2010年から2020年までの10年間では、269店舗から805店舗と3倍近い店舗数の伸びを示しています。
検討
さくら薬局グループ、アイングループ、クオールグループの大手調剤薬局3グループについてM&Aの推移をたどってきましたが、どの調剤薬局グループもM&Aを経営手段として重視していたことがわかります。
このことから、さくら薬局グループがM&Aを積極的に行ったこと自体については特異なものではなかったと考えられます。
しかし、それにもかかわらず、アイングループやクオールグループとは異なり、さくら薬局グループは経営破綻してしまいました。
それでは、なぜさくら薬局グループだけが破綻したのか、次では経営破綻の原因を検討したいと思います。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
さくら薬局グループが経営破綻した原因と経緯
さくら薬局グループが経営破綻した主たる原因は、M&Aのやりすぎによるものです。
また、副次的な原因としては次のものが挙げられます。
- 非公開化による資金調達の困難と多額の借入
- 新型コロナウイルスの拡大による売上高減少
- 調剤報酬の引下改定
ここでは、以上のような経営破綻の原因について解説するとともに、さくら薬局グループが経営破綻した経緯とその後の流れについても簡単に触れたいと思います。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
M&Aのやりすぎ
さくら薬局グループが経営破綻した最大の原因は、M&Aのやりすぎであると考えられます。
2008年にMBOにより上場廃止をした際の資料には次のような記載がありました。
「投資効率の悪化に伴い収益が減少し、利益予算を達成できないなど、経営環境は極めて厳しくなっております」
「そもそも調剤薬局業界は規制業種であり、国の方針として医療費削減が不可避の状況下で、上場企業の使命である増収増益をはかることは非常に困難な状況となっています」
「既存薬局をめぐるM&A取引による争奪戦は熾烈を極め、規模の利益を追求した拡大戦略が厳しい価格競争を引き起こして業界各社の足元の収益を圧迫することは確実視されつつあり、拡大戦略が将来の収益向上に確実につながるのか不透明な状況となっています」
さくら薬局グループが破綻する10年以上前の2008年の時点で、このような厳しい経営状況の認識が示されています。
この認識からは、上場を廃止しM&Aを抑制して経営を立て直す方向に進むようにも受け取れます。
しかし、さくら薬局グループは、その後も他社と同様にM&Aを行って店舗数を増加させてきました。
情報が公開されていないため具体的にどのようなM&Aを行ったかは明らかにされていませんが、他社の事例で注目すべきものがあります。
それは、クオールが2013年3月に行ったアルファームの子会社化の事例です。
この事例ではクオールが40億円余りを費やしていますが、アルファームは2012年3月期で売上高約48億円、営業利益1.5億円、純資産4.9億円の会社でした。
このように、M&Aの争奪戦に勝つために非常に大きなプレミアムをつけた実例があります。
この例は極端だとしても、一般的に他の業種と比べて調剤薬局のM&Aではプレミアムを高くつける傾向があります。
そのため、他社との争奪戦の中で価値に見合わない高額なM&Aが行われた可能性はあると言えるでしょう。
さくら薬局グループも他社と同様のペースで店舗数を増加させていたことを考えると、規模を拡大するために無理をして高額な買収をやりすぎていたことは十分に考えられます。
さくら薬局グループは、金融機関から買収資金を借入れることで返済額を上回るM&Aを続けた結果、巨額の負債を抱えて経営破綻しました。
M&Aを行えば見かけの店舗数や売上高が増加しますが、同時に負債の額も増加するため、自社の資金力を超えたM&Aのやり過ぎは経営破綻の危険性があることを示しています。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
副次的原因①非公開化による資金調達の困難と多額の借入
経営破綻に至った副次的な原因として、さくら薬局グループが上場を廃止して非公開会社化していたことが挙げられるでしょう。
非公開会社になるということは、新株を発行して資金調達することが難しくなることを意味します。
そのため、資金調達は主として金融機関からの借入れに頼ることになります。
さくら薬局グループもM&A資金を金融機関からの借入れに依存していたため、多額の借入金を抱えて返済不能になってしまいました。
副次的原因②新型コロナウイルスの拡大による売上高減少
新型コロナウイルスの感染拡大も深刻な影響を与えています。
緊急事態宣言の発令により不要不急の外出自粛が要請された結果、通院する人数が減り、薬局の利用者数も減少してしまいました。
また、処方薬を病院内で渡すことも増えたため、これも薬局の売上を減らす原因となりました。
副次的原因③調剤報酬の引下改定
調剤報酬の引下改定も、調剤薬局の売上に大きな影響を与えます。
調剤報酬は2年に1回改定されていて引下げとなる傾向がありましたが、特に2022年の改定では、同一グループの保険薬局の数が300以上の場合は調剤基本料が10点のマイナス改定でした。
これは、さくら薬局グループのような大規模な調剤薬局チェーンにとって厳しい結果となりました。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
経営破綻の経緯とその後
さくら薬局グループが経営破綻した経緯とその後の流れを簡単にまとめました。
事業再生ADRによる再建を図る
さくら薬局グループは、次のM&A資金を借入れるための担保として、取得した調剤薬局の調剤報酬債権を差し入れていました。
ところが、新型コロナウイルス流行の影響で受診控えが進んだ結果、薬局の調剤報酬債権も減少して資金繰りが悪化したことでこの手法を続けることができなくなり、2022年2月には経営再建のために事業再生ADRを申請しています。
事業再生ADRでは債権者すべての合意が必要ですが、これについては2023年1月26日付けで事業再生計画案が成立したことが発表されています。
不正請求疑惑の発覚
経営再建中の2022年10月、さくら薬局グループが調剤報酬を不正請求していた疑惑が報じられました。
2022年の改定では、同一グループで300店舗以上の場合に調剤基本料が引下げられましたが、これを回避するために一部の薬局を実質的に支配する他社の傘下としてグループから外したというものです。
この報道の数日後、さくら薬局グループに大きな発表がありました。
投資ファンドによる買収
2022年10月14日、日本産業推進機構グループ(NSSK)がさくら薬局グループのクラフト株式会社の全株式を譲り受けるとの発表がされました。
これによりさくら薬局グループは従来の経営陣の手を離れ、NSSKの傘下で経営再建を目指すことになりました。
スギ薬局との業務提携を発表
NSSKによるさくら薬局グループの株式譲受は2023年3月30日付けで行われましたが、同じ日にスギ薬局とさくら薬局グループが業務提携をすることが発表されました。
この発表当時でスギ薬局が1500店舗以上、さくら薬局グループが850店舗以上であり、合計すると2500店舗近い規模のドラッグストア・薬局グループが誕生しました。
このように、NSSKの支援を受けたことでさくら薬局グループの経営再建は今も進められています。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |
まとめ
この記事では、さくら薬局グループの事例について検討することで、M&Aをやりすぎることの危険性を見てきました。
M&Aは本来であれば効果的な経営手段であるとともに、欠くことのできない手法でもあります。
しかしながら、すべきでないM&Aをやりすぎれば最悪の結果に至ることが明らかになりました。
そのため、M&Aを実行する際は、専門家を交えて十分な調査・検討を重ねた上で行うことが望ましいと言えるでしょう。
M&Aをする際は、まず専門家に相談することをおすすめします。
| M&Aトラブル総合TOPPAGE |
| 表明保証違反損害賠償TOPPAGE |
| M&Aトラブル 総合案内ページ |
| M&Aトラブル類型 紹介総合案内ページ |