不正競争防止法違反の警告書が届いた場合どうすれば良いか
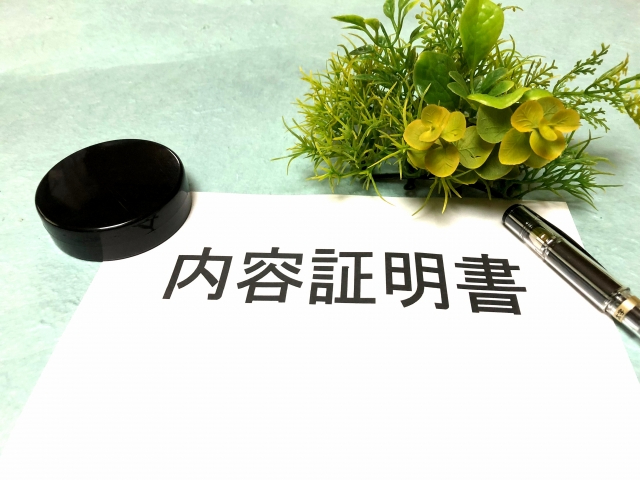
不正競争防止法違反の警告書とは
そもそも不正競争防止法とは
不正競争防止法は、企業間の公正な競争を維持し、営業秘密や知的財産を保護するための法律です。
この法律は、他人の営業上の成果や信用を不正に利用する行為を禁止し、損害賠償や差止請求を通じて被害者を救済することを目的としています。
具体的には、営業秘密の不正取得・使用・開示(第2条1項7号~9号)、商品形態や商標に類似する表示の使用(同1号~3号)など、広範な行為が対象です。
企業間では、転職・取引終了・下請け関係の解消などのタイミングで、情報の持ち出しや顧客引き抜きが疑われることが多く、その際に「不正競争防止法違反の警告書」が送られることになります。
警告書が送付される典型的なケース
警告書が送られるのは、主に以下のようなケースです。
| 区分 | 典型的な状況 | 想定される指摘内容 |
| 元従業員 | 退職時にデータを持ち出し、転職先で利用 | 営業秘密の不正使用、顧客引き抜き |
| 取引先 | 契約終了後も情報を利用して自社製品を開発 | 技術情報の不正利用 |
| 競合企業 | 類似デザインやブランドを使用 | 商品形態模倣、混同惹起表示 |
| フリーランス・委託先 | 契約終了後に得た情報を他社案件に流用 | 営業秘密侵害、信用毀損 |
これらのケースでは、警告書により「行為の中止」「損害賠償」「謝罪」などが要求されることが多く、対応を誤ると訴訟や仮処分に発展するおそれがあります。
警告書に記載される主な内容(違反行為・法的根拠・要求事項)
不正競争防止法違反の警告書には、一般的に以下のような構成要素が含まれます。
| 項目 | 内容例 |
| 違反の主張 | 「貴社(貴殿)は弊社の営業秘密を不正に取得・使用した」など |
| 法的根拠 | 不正競争防止法第2条第1項各号、第3条(差止請求)、第4条(損害賠償)など |
| 要求事項 | 行為の中止、損害賠償金の支払い、謝罪広告、誓約書提出 |
| 期限 | 「本書面到達後〇日以内に回答なき場合は法的措置を講じる」など |
| 代理人弁護士名 | 弁護士名・事務所名が記載されることが多い |
このように、警告書は事実認定・法的評価・要求内容が明確に示される正式な「紛争予告書面」としての意味を持ちます。
したがって、単なる警告や意見ではなく、将来の訴訟や仮処分に備えた証拠として機能することを理解しておく必要があります。
不正競争防止法違反とされる行為の類型
営業秘密の持ち出し・利用
営業秘密とは、「秘密として管理され(秘密管理性)」「事業活動に有用であり(有用性)」「公然と知られていない(非公知性)」情報を指します(不競法2条6項)。
退職や取引終了の際、顧客リスト、原価表、設計図などをUSBやクラウドに保存して持ち出す行為が典型です。
多くの場合、当人には「自分が作成した資料だから」という意識があり悪意は乏しいものの、法的には会社の財産として扱われ、刑事告訴につながることもあります。
顧客情報や技術情報の流用
顧客名簿、価格表、設計仕様書、ノウハウ資料などは、業種によっては企業の最重要資産に該当します。
これらを転職先や他社に提供することは、不正競争防止法第2条1項7号の「不正取得行為」または同8号の「不正使用行為」に該当し得ます。
特に、クラウド共有やスマートフォン同期などにより、本人の自覚なくデータが残っているケースも多いため、調査と説明が不可欠です。
元従業員による競業・引き抜き行為
退職した従業員が、転職先で前職の取引先や顧客を勧誘する行為は、競業行為または営業秘密の使用として問題視されることがあります。
以下のような状況では「不正競争」と評価される可能性があります。
- 退職直前に顧客リストをダウンロードしていた
- 転職後すぐに同一顧客へ営業している
- 同業他社への転職を前提に情報を持ち出した
一方で、単なる「人的つながり」や「記憶による営業」であれば違法とはされない場合もあり、事実関係の精査が重要です。
商品形態・表示の模倣行為
不正競争防止法は、商品パッケージ・名称・ロゴなどの「表示」を保護します。
類似デザインを用いて消費者に誤認を生じさせる場合(混同惹起行為)は、法第2条1項1号に該当します。
また、商品の形態(形・色・デザイン)を模倣して販売する行為も法第2条1項3号の「商品形態模倣行為」として禁止されています。
特にECサイトやOEM取引などで模倣指摘がなされることが多く、知的財産権(商標・意匠)との関係も慎重な検討が求められます。
なぜ不正競争防止法違反=営業秘密を持ち出したと発覚したのか?
不正競争防止法違反が疑われる場合、相手方企業は社内調査を経て証拠を収集しています。
たとえば以下のような手段で「発覚」することが多いです。
- 社内サーバーやアクセスログにより、退職前の大量データダウンロードを確認
- 退職者の転職先から類似資料・営業メールが流出
- 元顧客から「前の会社の資料を使っていた」と通報を受ける
- クラウドストレージのアクセス履歴から使用痕跡を発見
つまり、警告書が届く段階で、相手方は一定の証拠を確保していることが多く、軽率な否認や感情的な反論は危険です。
どの情報が実際に流用されたのか、どの資料が本人の私物か、専門家の立場から法的評価を行うことが不可欠です。
警告書を受け取った際に確認すべきポイント
送付元(会社・代理人弁護士)の確認
まず、誰から送られてきた警告書なのかを確認します。
送付元が企業の法務担当者名義であれば内部処理段階であり、弁護士名義であれば法的措置前提の段階といえます。
弁護士名・事務所名が明記されている場合は、すでに証拠整理が進んでいる可能性が高く、速やかに自社側も専門家を立てる必要があります。
違反とされる具体的行為の特定
警告書において「不正競争防止法違反」と書かれていても、その内容が具体的に特定されていないことがあります。
以下の観点で確認すると整理しやすいです。
- どの資料・データが問題とされているのか
- いつ、どの手段で取得・使用したと主張されているのか
- どの法律条項(第2条第1項第〇号)を根拠としているのか
行為の特定が曖昧な場合には、弁護士を通じて相手方に確認・照会することも有効です。
証拠・根拠資料の有無と内容の精査
警告書に「証拠を添付」している場合、その信憑性や取得経緯を慎重に確認します。
また、証拠が示されていない場合でも、相手方がどのような情報を把握しているかを推測し、社内の資料・メール・クラウド記録などを保全します。
調査時は、以下の点を整理して弁護士に共有すると分析がスムーズです。
| 確認項目 | 内容 |
| 持ち出した可能性のある資料 | ファイル名、保存媒体、時期 |
| 使用が疑われている資料 | 転職先・取引先での使用状況 |
| 社内管理体制 | 秘密情報のアクセス制限、返却手続き |
| 対応履歴 | 退職・契約終了時の説明記録 |
回答・対応期限の確認と記録化
警告書には、「〇日以内に回答がない場合は法的措置を取る」との文言があることが多いです。
期限が短い場合でも、焦って回答すると不利な内容を認めてしまうリスクがあります。
まずは期限を控え、相手方への連絡は弁護士を通じて「確認中であり、追って回答する」と伝える程度にとどめるのが安全です。
また、受領日・発送日・封筒などは証拠として保存しておくことが望ましいです。
慌てて対応してはいけない理由
回答や謝罪文が不利な証拠となるリスク
不正競争防止法違反の警告書を受け取った際、焦って「誤解です」「すぐに削除します」などと自己判断で返信してしまうケースがよくあります。
しかし、これらの記載は後に「行為を認めた証拠」として裁判で提出される可能性があります。
特に次のような記載は注意が必要です。
- 「知らずに持ち出してしまった」
- 「一部のデータは使いましたが、問題ないと思いました」
- 「すでに削除しましたのでご容赦ください」
これらは一見誠実な対応のように見えますが、相手方から見れば「不正取得・使用の事実を自白した」と評価されかねません。
法的リスクを理解せずに送付する文面は、後の防御を著しく困難にします。
交渉・訴訟の前提となる「証拠作り」への利用可能性
警告書のやり取りは、そのまま訴訟での証拠資料となります。
相手方は回答内容を分析し、「認めた部分」「矛盾する部分」「曖昧な説明」などを訴状の根拠として引用します。
したがって、初期対応段階では「感情的な説明を避け、法的に整合する記録を残す」ことが重要です。
弁護士を介して文面を整理し、争点を限定することにより、訴訟リスクを最小化できます。
弁護士を通じた初期対応の必要性
不正競争防止法違反に関するトラブルは、民事的損害賠償だけでなく刑事告訴に発展することもあります。
そのため、初期段階での一言一行が重大な結果を招く可能性があります。
弁護士を介入させることで、次のような利点があります。
| 項目 | 弁護士が行う対応例 |
| 警告書の法的評価 | 指摘内容が不正競争防止法に該当するか分析 |
| 証拠の整理 | 社内データの流出有無を確認し、保全資料を確定 |
| 応答書作成 | 不利な表現を避けた法的立場の明示 |
| 相手方との交渉 | 事実関係を限定し、感情的対立を抑制 |
警告書対応は、法的知見がなければ損害を拡大させるおそれがあります。必ず専門家の関与を受けてください。
適切な初期対応の流れ
弁護士への相談・代理依頼
警告書を受領したら、まず弁護士に速やかに相談します。
相談時には、以下の資料を準備しておくと対応が円滑です。
- 警告書原本および封筒
- 警告書に記載された事実関係に関する社内記録
- 関連するメール・チャット・クラウドログ
- 退職・取引終了に関する契約書や合意書
弁護士はこれらを基に、事実確認・法的評価・対応方針を立案します。
代理人として交渉を任せることで、企業間交渉が冷静かつ法的に整理された形で進められます。
社内調査と関係資料の保全
警告書の受領後、社内で速やかに関係者へのヒアリングと資料保全を行います。
特に、証拠データの改ざんや削除は、後に不利な推定を招くため避ける必要があります。
調査時の主な観点は以下のとおりです。
| 調査項目 | 内容 |
| アクセス履歴 | 問題のデータに誰が・いつアクセスしたか |
| 保存状況 | USB・クラウド・メール送信の有無 |
| 利用経緯 | 転職先や外部での利用履歴 |
| 管理体制 | 社内で秘密管理措置が取られていたか |
これらを整理することで、仮に裁判に至った場合でも合理的な説明を行うことができます。
応答書の作成と送付方針の検討
応答書(回答書)は、警告書に対して自社の立場を明示する文書です。
弁護士が作成する場合、通常は以下のような構成を取ります。
- 警告書の受領および検討中である旨
- 事実関係の確認中であり、現時点での法的評価は未確定である旨
- 不正競争防止法違反を否定する理由(必要に応じて)
- 不当な請求に対する抗議・反論
- 今後の連絡は代理人を通じて行う旨
この応答書は、今後の交渉方針を決定づける文書であり、安易な謝罪や譲歩は避けなければなりません。
争うか交渉・和解かを選択する
警告書対応の最終段階では、「徹底して争うのか」「交渉・和解により早期解決を図るのか」を判断する必要があります。
この判断は、単に感情や印象で決めるのではなく、法的リスクと経済的損失の両面からの合理的な検討に基づくべきです。
一般的には、以下の要素を総合して方向性を決定します。
- 相手方の主張に法的根拠があるか
- 相手方が証拠をどの程度把握しているか
- 自社側で反証資料をどこまで揃えられるか
- 訴訟や仮処分に発展した場合の損害・コスト
- 今後の取引関係や社会的信用への影響
これらを踏まえて弁護士と協議し、現実的なリスクコントロールを行うことが重要です。
交渉または和解を選択する場合の判断基準
警告書対応の目的は、あくまで「法的リスクを限定し、ビジネス上の損失を最小化すること」です。
したがって、事実関係や証拠の強弱を踏まえて、交渉または和解を選択することもあります。
交渉方針の目安は以下のとおりです。
| 判断基準 | 方針 |
| 証拠が乏しく、法的根拠が不明確 | 争う姿勢で応答し、根拠開示を求める |
| 一部事実を認めざるを得ない | 損害範囲を限定し、和解金額を最小化する |
| 訴訟リスクが高い | 早期和解を検討し、誓約書提出で終結を図る |
弁護士を通じた交渉であれば、感情的対立を避けつつ、法的に整合した「落としどころ」を見いだすことが可能です。
また、交渉過程を記録・整理しておくことで、仮に訴訟へ移行した際にも、誠実な対応の証拠として有利に働くことがあります。
訴訟・仮処分に発展する場合の留意点
差止請求・損害賠償請求の法的リスク
不正競争防止法に基づく請求には、主に「差止請求」「損害賠償請求」「信用回復措置請求」の3類型があります。
訴訟に発展した場合、損害額の算定や営業秘密該当性の立証など、専門的争点が多数生じます。
また、裁判所は秘密管理体制やアクセス制限措置を重視するため、企業側の情報管理の実態が重要な判断材料になります。
仮処分申立てに対する迅速な対応
営業秘密侵害の疑いがある場合、相手方が「仮処分命令」を申し立てることがあります。
仮処分では、訴訟よりも迅速に「利用差止」「資料返還」などの命令が出される可能性があり、対応の遅れは事業に重大な影響を及ぼします。
弁護士を通じて即時に反論書を提出し、必要に応じて「疎明(証拠提出)」を行うことが必要です。
裁判所での主張立証と証拠確保の重要性
裁判では、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の三要件を満たすかが中心的争点になります。
企業側がこれらの要件を適切に証明できない場合、営業秘密とは認められず請求が棄却されることもあります。
したがって、早期の段階でアクセス権限・社内ルール・退職手続きなどの資料を整理し、証拠体系を整備することが防御の鍵となります。
元従業員・競業関係者とのトラブルで多い事例
転職先での営業活動が不正競争とされたケース
元従業員が転職後すぐに前職の顧客へ営業を行い、「顧客情報の使用」と指摘される事例があります。
この場合、実際に顧客リストを利用したか、単なる記憶による営業かが争点となります。
裁判では「記憶による顧客勧誘」は原則自由とされていますが、資料持ち出しが確認されると不正使用と判断されやすい傾向があります。
社内データの持ち出しをめぐる紛争
USBやクラウドにデータを保存して退職した従業員に対し、会社が損害賠償を請求する事例も多く見られます。
特にクラウド同期サービス(Google Drive、OneDriveなど)は、本人の認識が薄いまま自動でデータが残ることがあり、トラブルを複雑化させます。
このような場合、削除・返還の履歴を整理し、誠実に対応することが有効です。
顧客名簿の利用を理由とした損害賠償請求事例
顧客名簿を利用したとされる訴訟では、実際の利用状況と損害の因果関係が問題となります。
裁判例では、単に顧客が離反しただけでは損害が認められず、「名簿の使用により営業機会を喪失した」と認定される必要があります。
このため、元従業員側も「偶発的な取引」であったことを立証できれば、責任を限定できる場合があります。
弁護士に相談すべきタイミング
警告書受領直後に確認すべき事項
不正競争防止法違反の警告書を受け取った段階で、最も重要なのは「早期に弁護士へ相談するタイミングを逃さないこと」です。
初動が遅れると、証拠保全や交渉対応が後手に回り、仮処分や損害賠償請求への対応が難しくなります。
特に以下のような場合には、即時に弁護士への相談が必要です。
| 状況 | 対応の必要性 |
| 警告書に「法的措置」「仮処分」などの文言がある | 緊急対応が必要。数日以内の相談が望ましい |
| 警告書が弁護士名義で届いている | 既に訴訟準備段階にある可能性が高い |
| 相手方が具体的証拠を提示している | 証拠保全・反証準備を早期に開始すべき |
| 自社関係者が関与を疑われている | 社内調査と事実確認を弁護士と連携して進める |
弁護士は、これらの状況を踏まえて「今どの段階か」「どの程度緊急性があるか」を即座に判断します。
初期対応のスピードが、最終的な解決コストを大きく左右することを理解しておくことが重要です。
弁護士に相談する際に整理すべき相談内容
相談時に弁護士へ伝えるべき基本情報
警告書を受け取ったら、まず弁護士に以下の情報を整理して伝えることが重要です。
事実関係が明確であれば、弁護士は法的評価と交渉方針を早期に立案できます。
- 受領日時と送付者(会社・弁護士の別)
- 指摘内容と要求事項の概要
- 問題とされる行為が実際に存在するか否か
- 関係者・関係資料の有無
- 自社が実施済みまたは検討中の対応(削除・返還など)
これらを可能な限り正確に共有することで、弁護士は「争うか、和解を目指すか」という初期戦略を即時に設計できます。
弁護士が行う警告書の分析と交渉戦略
弁護士は、警告書の構成・引用条文・文言の精度を分析し、相手方がどの程度法的準備を整えているかを見極めます。
その上で、次のような戦略を立てて対応します。
| 状況 | 対応方針 |
| 相手方の主張が抽象的 | 詳細な根拠の開示を求め、交渉を主導する |
| 証拠が提示されている | 争点を限定し、反証資料を準備する |
| 仮処分の可能性がある | 即時に反論書を作成し、リスクを回避する |
| 和解の余地がある | 損害賠償の範囲を限定し、合意を検討する |
弁護士が介入することで、法的主張と交渉戦略を明確に整理でき、紛争の方向性をコントロールできる点が大きな利点です。
弁護士が介入することによる効果(交渉・訴訟リスクの軽減)
弁護士の関与によって、以下のような具体的な効果が得られます。
- 不当な請求・過剰な要求を抑止できる
- 証拠の開示を求め、事実関係を精緻に整理できる
- 法的に整合した応答書を作成できる
- 相手方の訴訟提起を抑止する交渉が可能となる
さらに、弁護士が正式に代理人として通知を行えば、以降のやり取りはすべて弁護士経由となり、
企業担当者が直接対応する必要がなくなるため、心理的・業務的負担も軽減されます。
まとめ:不正競争防止法違反の警告書への対応で最も重要なこと
感情的に対応せず、事実確認と法的整理を優先する
警告書を受け取ると、多くの企業が「誤解を解きたい」「すぐに謝って済ませたい」と考えますが、これが最も危険です。
感情的な反応ではなく、まずは事実確認と法的評価を冷静に行い、どの部分に争点があるのかを整理することが先決です。
弁護士と連携し、早期にリスクを限定化する
弁護士が関与すれば、法的根拠の有無を精査した上で、争うべき点・譲歩すべき点を合理的に判断できます。
早期に代理人を立てることで、訴訟・仮処分などの事態を回避し、最小限のコストで解決することが可能です。
企業としての再発防止体制を構築する
トラブルを機に、秘密管理体制の見直しを行うことも重要です。
社内教育、アクセス権限の限定、退職時の情報返還確認などの仕組みを整えることで、同様の紛争を未然に防ぐことができます。
不正競争防止法は「攻め」と「守り」の両面を意識する法領域であり、継続的な体制整備が企業の信頼を支えます。





