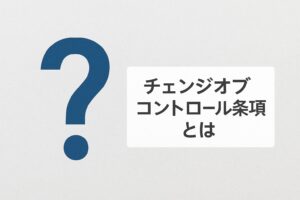M&A後の競業避止義務違反とは?会社・元社長・元従業員が負う法的義務を解説

競業避止義務違反とは
競業避止義務違反とは、法律または契約によって課された「競合する事業を行ってはならない」という義務に違反する行為を指します。
M&Aの文脈においては、会社や事業を譲渡した側(元社長や譲渡企業)が、譲渡した事業と競合する事業を新たに始めたり、競合他社に協力したりすることで、買主(譲受企業)の利益を不当に害する状態を意味します。
この違反行為は、単なるマナー違反や倫理上の問題にとどまりません。後述するように、法律(会社法など)や当事者間の契約に基づく明確な義務違反であり、差止めや損害賠償請求といった法的な責任追及の対象となる重大な不正行為です。
なぜ競業避止義務が設けられるのか
競業避止義務が設けられる主な目的は、譲受企業が取得した事業価値を保護し、M&Aの実効性を確保することにあります。
M&Aでは、譲受企業は対価を支払って顧客基盤、ノウハウ、ブランド、営業秘密といった無形資産を含めた事業全体を取得します。しかし、もし譲渡企業側の関係者が同じ市場で競業を開始すれば、これらの資産価値は容易に毀損されかねません。特に元経営者や幹部従業員は、既存顧客との関係や業界知識を活用して短期間で競合事業を立ち上げることが可能であり、譲受企業にとって重大な脅威となります。
競業避止義務は、こうした不公正な競争を防止し、買収の目的である「事業の継続的成長」や「投資回収」を実現するための法的・契約的保護手段として機能しているのです。また、取引の公正性を担保し、M&A市場全体の信頼性を維持する役割も担っています。
M&A後に問われる競業避止義務とは
M&Aの場面で問われる競業避止義務は、一般的な従業員の退職時に課されるものとは、その重要性や強度が大きく異なります。
通常の退職の場合、義務の主な目的は企業の機密情報保護にありますが、M&Aではそれに加え、事業そのものの価値(のれん)が巨額の対価で取引されるという特殊性があります。そのため、法律(会社法)や契約によって、より長期間かつ広範囲にわたる、強力な義務が課されるのが一般的です。
以下では、M&A特有の競業避止義務について、その重要性、範囲の設定方法、契約書での注意点を解説します。
M&Aにおける競業避止義務の重要性と企業側の目的
M&Aにおいて競業避止義務が重要視されるのは、譲受企業が取得する事業価値の大部分が「人的資産」や「顧客関係」といった流動的要素に依存しているためです。
譲渡企業の元経営者や幹部社員は、長年培った顧客との信頼関係、業界ネットワーク、独自ノウハウを保有しています。これらの人物が競業を開始すると、譲受企業は実質的に「顧客なき事業」を取得したに等しい状況に陥る危険があります。
したがって、買主(譲受企業)にとって、競業避止義務を適切に設定することは、M&Aプロジェクトの成否を左右する極めて重要な要素だといえるでしょう。
企業側の具体的な目的は、主に以下の4点に集約されます。
| 投下資本の回収と事業計画の達成 | M&Aに投じた資金を回収し、期待したシナジー効果を実現するため、一定期間は競合の脅威なく事業を軌道に乗せる必要性がある。 |
| 「のれん(営業権)」の保護 | 顧客リストや取引関係、ブランド価値といった、買収した事業の中核的価値が流出・毀損されるのを防ぐ。 |
| キーパーソンの引き抜き防止 | 元社長や役員が、主要な技術者や営業担当者を引き抜いて独立するといった事態を防ぐ。 |
| 機密情報・ノウハウの流出防止 | 譲渡された事業に関する技術、価格情報、経営ノウハウなどが競合事業に利用されるのを防ぐ。 |
これらの目的を達成するため、競業避止義務はM&A契約における最重要条項の1つとして扱われます。
競業避止義務違反にあたる行為はどこまで制限されるか
競業避止義務違反の判断では、「どこまでが禁止される競業行為か」という線引きが最大の争点となります。義務の範囲を過度に広く解釈すれば職業選択の自由を侵害し、逆に狭く解釈すれば実効性を失います。
判断にあたっては、契約条項の文言、事業の実態、当事者の行動態様、譲受企業の被害の程度などを総合的に考慮します。重要なのは、「形式的な業種の違い」ではなく、「実質的な競合関係の有無」です。
以下では、具体的な競業行為の類型、禁止範囲の実際、そして多様な行為態様ごとの判断基準を詳述します。
競業行為の例と判断基準
競業行為として典型的なものには、以下のような類型があります。
直接的な競業
同種事業を営む新会社の設立・経営や、競合他社への就職・役員就任、そして譲渡事業と同一商品・サービスの販売開始などがあげられます。
間接的な競業
競合企業への出資・融資による支援は典型例です。競合企業の顧問・コンサルタントとして関与することや、家族名義での事業展開(実質的に本人が経営する場合)も間接的な競業行為といえるでしょう。
顧客・従業員への働きかけ
譲渡事業の顧客に対する取引勧誘や譲受企業の従業員に対する引き抜き行為、取引先に対する取引停止の働きかけなどです。
判断基準
競業行為に該当するかは、以下の4つの要素を総合考慮して判断されます。
| 事業の同一性 | 商品・サービスの種類、市場、流通経路、顧客層の重複度 |
| 実質的競合性 | 譲受企業の事業に与える影響の程度 |
| 行為の態様 | 積極的な顧客奪取意図の有無、営業秘密の利用状況 |
| 契約条項との整合性 | 明記された禁止行為に該当するか |
注意したいのは、形式的に業種が異なっていても、実質的に同一市場で競合する場合は競業行為と判断されるという点です。
後掲のウェブサイト譲渡事件(東京地裁平成28年11月11日判決)では、「ロリータファッション」と「ガーリーファッション」の区別が争われましたが、顧客層の重複や営業手法の類似性から競業行為と認定されました。
禁止される業種・地域・期間
競業避止義務の制限がどこまで有効とされるか、すなわち禁止される業種・地域・期間については、個別具体的な事情に応じて判断されます。
業種
禁止される業種の範囲は、譲渡された事業と「実質的に競合する範囲」に合理的に限定される必要があります。全く関連性のない異業種での活動まで禁じることはできません。
地域
事業の実態に即して設定されます。顧客が関東一円にしかいない事業で「全世界」を対象とすることは、通常、合理的とは認められません。しかし、ECサイトのように地理的制約のない事業では、日本全国を対象としても合理的と判断される場合もあります。
期間
禁止される期間は義務の重さや対価の額によって変動します。一般従業員の退職後の競業避止義務であれば1年〜2年程度が有効性の目安とされます。一方で、M&Aで高額な譲渡対価を受け取った元社長(オーナー)の場合は、より重い義務を負うと解され、3年〜5年、場合によってはそれ以上の禁止期間でも不合理ではないと判断されることもあります。
M&A事業を譲渡した会社が負う競業避止義務
ここからは、M&Aにかかわる競業避止義務の内容について、「譲渡企業」と元社長・元従業員にわけて解説します。
まずは、譲渡企業が会社として負う競業避止義務です。
事業譲渡によるM&Aを実施した場合には、会社法第21条1項〜3項によって競業行為が制限されます。違反した場合には、民法・会社法に基づいて行為を差止めた上で、損害賠償請求も認められます(詳細は後述)。
なお、会社ではなく、個人事業主が営業を譲渡した場合も同様に規制されます(商法第16条)。
事業譲渡会社の競業避止義務で注意したいのは、競業禁止の効果が及ぶ範囲です。以下で解説するように、悪質なケースでない限り、常に一定範囲の地域・期間にしか及びません。
競業避止義務の原則:同一地域内で20年間
事業を譲渡した日から20年間に限り、同一の市区町村および隣接市区町村での競業は禁じられます(会社法第21条1項)。違反した場合には、民法・会社法に基づく差止めのほか、損害賠償請求も認められます。
譲渡時の合意がある場合:最大30年に延長可
実際にM&Aで交わす契約書においては、会社法の規制頼みとせず、競業避止義務に関する条項を個別に加え入れるのが一般化しています。合意があれば、左記条項で競業禁止の期間を最大30年間とすることも認められています(同条2項)。
ただし、禁止期間の延長を行う場合には、引き換えに制限地域の範囲を縮小するなどしてバランスを取るのが一般的です。
「不正の競争の目的」は範囲無制限で禁止される
前述の通り、譲渡企業が負う競業避止義務には地域や期間の範囲が定められています。しかし、「不正の競争の目的」がある場合は例外であり、範囲の制限なく競業が禁止されます(会社法第21条3項)。
会社法上の「不正の競争の目的」の定義は、事実上の顧客を奪おうとするなど「事業譲渡の趣旨に反する目的で同一の事業をするような場合を指すもの」と解されています(大審院大正7年11月6日判決)。
例えば、譲受企業の信用をわざと貶めたり、商標権を侵害したりするような悪質なケースは、事業譲渡の趣旨に反することが明らかですので、期間・地域を問わず損害賠償責任が生じるといえるでしょう。
株式譲渡したケースで課される競業禁止の範囲は?
会社法第21条は事業譲渡のケースを規制する法律です。したがって「株式譲渡」によるM&Aを実行した場合には同条の規定が適用されません。
もっとも、個別の合意による競業避止義務は有効です。競業禁止の効果が及ぶ期間を2〜3年としつつ地域的範囲は業種等に応じて定めるなど、当事者の交渉によって禁止義務の内容を決めます。
補足すると、合意による競業行為の定義は「自ら営業すること」に留まらないのが普通です。投資や顧問を通じて「他社を支援すること」も禁止となるよう、契約書等の条項の文言をコントロールしなければなりません。
契約における明記内容と注意点
株式譲渡によるM&Aの場合、会社法のような法律の後ろ盾がないため、契約によって競業避止義務をコントロールしなければなりません。専門家である弁護士のレビューを受けながら慎重に条項を作成する必要がありますが、特に以下の点には注意が必要です。
| 禁止する事業内容の特定 | 「競合する一切の事業」といった曖昧な文言ではなく、「〇〇製品の製造・販売事業」のように、対象事業を具体的に特定する。 |
| 禁止行為の態様の網羅 | 「自ら事業を行う」ことだけでなく、「役員・従業員・顧問としての関与」「第三者への出資・融資」「ノウハウの提供」など、あらゆる形での関与を網羅的に禁止する。 |
| 地理的範囲と期間の明記 | 合理的な範囲で、対象地域(例:日本国内)と期間(例:クロージング日から3年間)を明確に定める。 |
| 義務の対価の明確化 | 義務を課すことへの見返り(代償措置)として、譲渡代金の一部がこの義務の対価であることを明記すると、契約の有効性が補強される場合があります。 |
競業避止義務に違反した会社に対する措置
M&A後の競業行為が発覚した場合には、会社自体に競業を取り止めさせる措置が必要です。考えられる措置として、以下の2つがあります。
履行強制+債務不履行による損害賠償
会社法21条違反の事実があれば、競業避止義務を履行するよう民法第414条に基づいて強制できます(東京高裁昭和48年10月9日判決等)。その上で、債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)に基づく損害賠償請求も認められます。
不正競争防止法に基づく措置
不正競争防止法第2条1項の行為類型に当てはまるような場合には、営業上の利益の侵害をやめさせる「差止請求権」(法3条)が認められます。侵害された利益については、金額を推定した上で損害賠償請求も可能です(法4条・5条)。
その他、被害の拡大防止等につながる以下のような権利も認められます。
書類提出命令(法7条)
侵害行為の立証もしくは損害額の計算のため、必要な書類の提出を命じられる。
営業秘密の民事訴訟上の保護等(法10条・13条等)
営業秘密について訴訟に関わる者に秘密保持命令を出せる他、当事者尋問を非公開にできる。
信用回復の措置(法14条)
営業上の信用を回復するのに必要な措置(謝罪広告等)を命じられる。
M&A後に元社長・元従業員が負う競業避止義務
次に、中小企業における競業トラブルで最も重要な論点となる、元社長あるいは元社員が負う「個人としての競業避止義務」を確認してみましょう。
以下のように、義務・制約の内容はポジションによって異なりますが、いずれも個別の合意で競業を禁止できる点に違いはありません。
元社長(退任した取締役)の負う義務
譲渡企業の元社長については、その在任中に「事業の部類に属する取引」をしようとする場合、株主総会の承認決議を要するとの定めがあります(会社法第356条1項)。左記規則を破り、競業の準備をしてからM&Aに踏み切ったとなれば、忠実義務(会社法第355条)・善管注意義務(会社法第330条・民法第644条)に違反するとして、損害賠償責任を負います。
では、退任後に競業を企てて実行したケースはどうでしょうか。
考えられるのは、退任時に交わした競業避止義務契約あるいは秘密保持誓約(契約)に基づく義務です。これに違反すれば、差止めや損害賠償を求められるのは当然です。また、個別の合意の有無に関わらず、不正競争防止法違反が認められる可能性もあります。
利益相反行為との違い
会社法第356条で同様に規制される「利益相反行為」は、会社が取引の当事者となるケースを前提としています。対する「競業行為」は、会社が関与せず、代わりに会社の顧客が取引の当事者となって、取締役の事業と会社がライバル関係に陥るケースを想定しています。
元従業員が負う義務
労働契約法第3条4項は「労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。」と定めています。この信義則に従うならば、元従業員の競業避止義務を帰結できるように思うかもしれません。
しかし、同条項は雇用契約を前提とする法律です。したがって、退職した元従業員の競業行為に対しては直接適用できません。元従業員が負う競業避止義務の内容は、就業規則や秘密保持契約、会社と個別に交わした誓約書等の内容から判断することになります。
会社個人間の競業避止義務の合意が有効であるためには、後述する6つの要件をすべてクリアする必要がありますが、判例は「元従業員の競業行為について、地域および期間を合理的な範囲で限定して競業禁止を要求することは有効」と判断するのが一般的な傾向です。
例えば、学習塾の非常勤講師が元勤務先の塾から430メートル離れた場所に自分の塾を開いたケースでは(大阪地裁平成27年3月12日判決、株式会社成学社事件)、会社側が従業員に対して「半径2キロ以内、退職後2年間の競業行為禁止」を義務付けていたことについて、裁判所は「有効」とみなしています。
一方、病院へ人材紹介する会社の一般社員が同業他社に転職したケースでは(大阪地裁平成28年 7月14日判決、リンクスタッフ元従業員事件)、会社側が従業員に対して「地域の制限がなく、退職後3年間は同業への転職を禁止した」誓約書について「無効」と判断しました。
M&A後に競業する元社長や元従業員への措置
M&Aの後に起こる競業トラブルの大半は、元社長(退任した取締役)等が個人的に行うものです。
その責任はすでに確認した通りですが、競業避止義務違反に対処する際は、まず法律違反に対する措置(パターン1)が可能か検討し、次に個別の合意や譲渡企業側の不利益等を根拠に措置できるか(パターン2)を確認します。
| 【パターン1】法律違反に対する措置 |
| ①不正競争行為に対する差止請求等
②在任中の背任行為に対する会社法上の措置 |
| 【パターン2】個別の合意に従った措置、譲受企業の不利益を根拠とする民事上の措置 |
| ③有効な合意に基づく競業避止義務違反への措置
④譲受企業の不利益を根拠とする民事上の措置 |
①〜④のいずれの場合でも、問題になるのは「違反の要件を満たしているか」です。
会社法や不正競争防止法に基づいて措置する場合には、競業とみなされる取引や、行った地域の要件を確認しなければなりません。大半のケースが当てはまる「個別の合意に反した」として対処する場合には、その合意自体が職業選択の自由を脅かしていないことが前提です。
以下では、①〜④の措置について、違反の要件と可能な措置を説明します。
①不正競争行為に対する差止請求等
競業する元社長等の行為を「不正競争」とするには、実態として「周知な商品等表示の混同惹起」(不正競争防止法第2条1項1号)や「営業秘密の侵害」(同4号~16号)に該当することが前提となります。
よくある後者の路線では、新事業に横流しされた顧客リスト、あるいは流用された技術やノウハウ等といったものが、解釈上「営業秘密」と呼べるかどうかが問題です。
もし買収した側の企業にとって有利な判断ができるようであれば、民事上の措置と共に刑事責任における法人との両罰規定(不正競争防止法第22条)等を予告し、圧力をかけて競業を取り止めさせられます。
不正競争防止法上の営業秘密とは
不正競争防止法上の営業秘密に該当するかは、「営業秘密管理指針」(経産省、令和7年3月改訂版)が規定する3つの要件で判断します。
・秘密管理性
秘密管理しようとする意思が明確に示され、合理的区分等の必要な措置があること。
・有用性
客観的に見て事業活動にとって有用であること。※行政処分歴等、反社会的な情報は該当しない。
・非公知性
一般的には知られていない、または容易には知り得ないこと。※公開情報や一般に入手可能な刊行物等で知り得る情報は該当しない。
秘密管理性の要件の注意事項
秘密管理性については、M&Aで特に注意したい要件があります。譲渡契約書において秘密保持契約(NDA)が適切に締結される等、譲受企業によって管理に関する意思が書面で明確にされていることが前提となる点です。さらに、競業している本人(元社長や元従業員)の認識可能性についても立証しなければなりません。
付け加えると、必ずしも不正競争防止法の措置の対象になるとは限らない点にも注意を要します。当事者間の信頼関係の程度や各当事者の利益等から、「不正の利益」また「譲受企業に損害を加える目的」だと判断できる証拠がある場合のみ、法律上の措置が取れると考えるべきです。
②在任中の背任行為に対する会社法上の措置
元社長が「在任中から背任行為を企てていた」と立証できる場合には、その会社に対する損害賠償義務が生じます。賠償金額は、元社長が競業で得た利益の額と推定されます(会社法第423条2項)。
また、任務懈怠による損害賠償責任の線でも、しかるべき代償を負担させる措置が可能です(会社法第423条1項)。
「事業の部類に属する取引」の解釈
会社法423条2項に基づいて措置する場合には、株主総会の承認を要するとされる「事業の部類に属する取引」の解釈に当てはまることが前提です。
現状では、取引と目的物(商品やサービスの種類)および市場(地域や流通のプロセス等)が一致すれば、上記取引に当てはまると考えられます。
取引と目的物、市場については、以下のように広く解釈することが可能です。
・取引と目的物の解釈
製造や販売を目的とする会社なら、原材料購入も競業になり得る(最高裁昭和24年6月4日判決)。
・市場の解釈
会社が進出予定を立てて具体的に計画している地域も該当する(東京地裁昭和56年3月26日判決)。
③有効な合意に基づく競業避止義務違反への措置
不正競争防止法や会社法で定める措置が取れないとすれば、競業している本人との合意に違反したとして、損害賠償請求を行う措置が考えられます。
個人との「競業避止義務の合意」が有効と判断される基準
すでに触れたように、個人との競業避止義務の合意は、相手の職業選択の自由を脅かさないよう配慮しなければなりません。また、合意を締結する理由・目的が十分であったかどうかも重要です。
上記2点を踏まえ、合意は下記の6つの要件を全て満たす場合のみ有効となります。
| 守るべき企業の利益 | その情報が営業秘密に匹敵するほどの価値が認められるか |
| 競業する者の地位 | 対象者の地位上、秘密情報に接することが出来たか |
| 地域的な限定 | 競業避止の合意につき、合理的な地域制限があったか |
| 避止義務の期間 | 競業避止の合意につき、合理的な期間制限があったか |
| 禁止行為の範囲 | 競業避止の合意につき、禁止行為の内容(職種等)が明確にされているか |
| 代償措置 | 競業避止の合意につき、賃金や役員報酬等で補償していたか |
④譲受企業の不利益・損失を根拠とする民事上の措置
①〜③のどの措置も選択できない場合には、④譲受企業が被った不利益等を理由に損害賠償請求(もしくは不当利得返還請求)を予告し、暗に競業をやめるよう促す手段が考えられます。
もっとも、競業行為と被った不利益との因果関係を証明するのは、相当困難と言わざるを得ません。事業内容やM&A実行時の契約内容から、弁護士に個別の勝ち筋を見つけてもらう必要があります。
M&A後の競業行為に関する判例
最近注目されたM&A後の競業を巡るトラブルを見てみると、競業であること自体は認められても、差止めや損害賠償が全面的に認められるのは難しいと分かります。参考になる判例を2件詳しく紹介します。
ウェブサイト譲渡を巡る競業行為差止等請求事件
中古衣料品売買サイトの譲渡を受けた原告が、被告が新しく立ち上げたネット販売事業につき、会社法第21条3項に言う「事業」であるとして、全面的な差止めと損害賠償を求めた事件です(東京地裁平成28年11月11日判決)。
当該事例では、サイトと共に譲渡したはずの顧客の連絡先に新規事業開始を知らせるメールが多数送付されていた事実等から、会社法第21条3項の「不正の競争の目的」があると認められました。その上で、各争点につき下記のように判断され、差止めと損害賠償請求が一部認められています。
判決では、事業の同一性(=譲渡の事実とその対象)が問題となりました。譲渡したサイトは「ロリータファッション」と「ガーリーファッション」の両方を取り扱っており、被告側は前者にかかわる事業のみ引継ぎしたと主張しました。その上で、新規で立ち上げた事業は後者にかかるものと言い張り、競業ではないと反論しています。
しかし実際には、契約書記載の譲渡対象物が古物商ノウハウから顧客の連絡先までの広範囲にわたっており、書面上「ガーリーファッション」を譲渡対象から除外する文言もありません。その他の事実等も踏まえ、裁判所は譲渡事業と新規事業が同一のものと認めています。
また、競業避止義務にかかる「黙示の合意」の有無も争点となりました。新規事業は「ガーリーファッション」を扱うものと認識している被告は、事業の同一性で説明した譲渡の条件につき、説明・了承を得ていたと言います。併せて原告が新規サイトの立ち上げを黙認していた事実より、競業避止義務を負わないことについて黙示の合意があったと主張しました。
この点、被告が立ち上げたサイトには「ロリータ」のキーワードが含まれている事実等からも、黙示の合意があったとは見なされていません。
上記判例は、ファッションジャンルの区別を裁判所にさせる異例のものです。しかし最終的には、「譲渡契約書その他の交付した書面の内容」と「被告の顧客の集め方」が決め手となり、原告に有利な判決が出ています。
注意したいのは、事業の範囲は被告から交付されている「買取ブランド一覧」とされ、差止めの範囲は左記に限定されている点です。損害賠償請求に至っては、被告によって顧客がどの程度奪われ、どの程度の粗利減少が見られるのか、この点を主張・立証できていないとして、請求額の3割程度しか認められていません。
洗剤販売事業の譲渡を巡る競業行為差止等請求事件
ドライマーク衣類の洗濯に使える溶剤を販売する控訴人(原判決の被告)が、本販売事業の譲渡先かつ負債支払いのコンサルタント会社であった被控訴人(原判決の原告)との間でトラブルになったケースです(東京地裁平成28年12月7日判決)。
譲渡業者の競業行為は、①溶剤製造の委託先に原告との契約破棄を求める、②類似名称の商品を扱い始める、③譲渡で原告側の顧客となった会社と取引再開する等、多岐に及んでいます。
原判決では、譲渡業者の行動、そしてコンサルタント契約を結ぶ際に交わした覚書の存在等から、会社法21条3項の「不正の競争の目的」があると認められています。
不正競争の目的があったことを理由に譲受業者の訴えを全面的に認めることも可能でしたが、実際にはごく限定的でした。譲渡業者による「②類似名称の商品を扱い始めた行為」がクローズアップされましたが、これを「周知表示の混同惹起行為」(不正競争防止法第2条1項1号)と認定しつつ、譲渡業者が商標を不正に使用している事実の範囲でしか請求は認められませんでした。
上記判例からは、「不正競争の目的」があると認められたからといって、買収した側の主張が特に広く認められるわけではないことが分かります。悪意のある競業でも、被害を解消していくには、一歩踏み込んで不正競争防止法違反を主張・立証する必要性を考えなくてはならないといえるでしょう。
M&A競業避止義務における独占禁止法上の問題点
最後に、競業避止義務との関連が深い独占禁止法の「企業結合規制」の問題について解説します。
M&A後の競業行為についてなんらかの措置を行おうとする場合、対象者(会社や元社長)の抵抗は避けられません。ここで気になるのは、当初課した競業避止義務について、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の「企業結合規制」に抵触すると主張される可能性です。
【企業結合規制とは?】
企業結合規制とは、市場における価格や供給数量をコントロールできる企業を出現させないよう、株式取得・役員兼任・合併・事業譲渡等を禁止または届出制とする規制です。独占禁止法では、株式の取得(10条)、役員の兼任(13条)、合併(15条)、共同新設分割・吸収分割(15条の2)、共同株式移転(15条の3)、事業譲渡(16条)等につき一定の要件のもと規制されています。
企業結合規制の詳細な判断基準や、規制対象外の結合を定めた「セーフハーバー基準」については、企業結合外ガイドライン(企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針)で定められていますので参照をおすすめします。
「企業結合規制」に抵触するケースは少ない
結論として、競業避止義務が企業結合規制に抵触し、独禁法違反となるケースは少ないと考えられます。
そもそもM&Aを実施する際には、必ず企業結合ガイドラインを参照して規制適用の有無を確かめます。規制されるのであれば、一定の要件のもと事前届出を提出する等、これを回避する方法を検討しているはずです。
実際のところ、中小企業同士のM&Aであれば、市場占有の度合いを示すHHI(ハーフィンダール・ハーシュマン指数)が規制基準に達しないのが一般的です。そうなれば、禁止される企業結合であるかどうか判断するまでもありません。
「不公正な取引方法」として扱われる可能性はある
注意したいのは、独禁法上問題とされるのが「企業結合による市場の独占化」に留まらない点です。競業避止義務においては、他に導入されている規制の1つである「不公正な取引方法」に該当する可能性が排除できません。
上記問題を扱ったものとして、産業見本市の開催者が競争事業者から開催権を譲り受けた事例が挙げられます。
これは、電子部品に係る有名見本市の開催権を譲受する企業が、譲渡企業に対し「当該見本市の開催時期および前後3か月以内」と時期を定め、同趣旨の見本市の開催を禁じる契約を課そうと検討していたケースです。
公取委の回答では、譲渡によってただちに競争が実質的に制限されるとは認められないとした上で、上記の競業避止義務が「拘束条件付取引」(昭和57年6月18日公取委告示第15号第12項)に該当する恐れがあるとしています。開催権の移転により見本市名称の使用を制限するだけであればまだしも、地域等を制限せず市の開催を全面的に禁止すれば、譲渡企業が競争単位として機能する可能性が閉ざされると考えられるためです。
本事例からは、買収される側の市場での地位等を鑑み、避止義務が度を過ぎないよう十分注意しなければならないと分かります。
まとめ
M&A後の競業行為は、会社法・不正競争防止法の他に個別の合意によっても制限されています。難しいのは、①違反の要件を、②競業の範囲、そして③具体的な被害を主張・立証する作業です。実例の多くは、②〜③に関する対応が十分であっても、差止めと損害賠償が認められる範囲は競業行為の根幹部分に限定されるのが一般的です。
競業の様態があまりに多様化している点を踏まえても、万一の時は弁護士による状況分析と措置の提案は不可欠と言わざるを得ません。言うまでもなく、最も重要なのはM&A実施時に書面で交わす契約内容です。
元社長や譲渡企業による競業が発覚した時、あるいは予期される時には、M&Aに詳しい弁護士にすぐ相談して判断を仰ぎましょう。