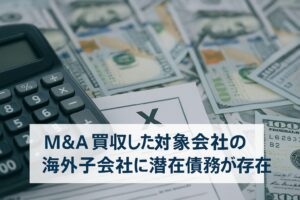非上場企業における自己株式取得のルールとは?取得方法やメリット・デメリットを解説

非上場企業にとって、自己株式取得は経営戦略の一つとして重要な手段です。自己株式取得は、企業が株主から自社の株式を買い戻す行為を指し、株主構成の変更や資本構成の最適化などを図るために行われます。
ただし、上場企業に比べて非上場企業では自己株式取得に関する情報が少なく、その手続きやルールに関する理解が不十分なことも少なくありません。
本記事では、非上場企業における自己株式取得の基本的なルール、取得方法、そしてそのメリットとデメリットについて詳しく解説します。
非上場企業における自己株式取得とは
自己株式取得とは、企業が発行した株式を自社の資金で株主から買い戻すことを指します。
日本ではかつて、自己株式取得は原則として禁止されていました。しかし、2001年の商法改正を背景に金庫株の保有が認められたことで、自己株式取得が可能となりました。
非上場企業の場合は、株主と直接交渉して株式を買い戻します。このように買い戻した株式は自社で保管され、「金庫株」と呼ばれます。金庫株の取得後は、そのまま保有しておくことも、消却(消去)することも可能です。
非上場企業における自己株式取得のメリット
非上場企業における自己株式取得の主なメリットについて、非上場企業側(買収側)と株主側(売却側)に分けて、順番に解説します。
非上場企業側(買収側)のメリット
非上場企業側(買収側)における自己株式取得の代表的なメリットを4つピックアップし、順番に解説します。
株主構成のコントロール
非上場企業にとって、株主構成を最適に保つことは非常に重要です。自己株式取得を行うことで、企業は株主構成を効果的にコントロールし、経営の安定化を目指せます。
自社株を買い戻すことで、経営陣は企業の意思決定プロセスにおける影響力を強化できます。これにより、経営戦略を迅速かつ確実に実行することが可能となります。特に、多くの株主が存在する場合、自己株式取得は経営権の分散を防ぐための有効な手段となります。
また、非上場企業では、一部の株主が経営に対して不安要素をもたらす場合もあります。例えば、企業の成長を妨げる発言を繰り返したり、短期的な利益を追求したりする株主の存在が挙げられます。自己株式取得を通じて、このような株主を排除することで、経営の安定を図ることができます。
事業承継における資金面のハードル低下
事業承継は企業の存続と成長にとって極めて重要です。特に非上場企業においては、次世代へのスムーズな引き継ぎが、企業の将来を大きく左右します。しかし、事業承継には多額の資金が必要であり、その資金調達は多くの企業にとって大きなハードルとなります。
自己株式取得は、この事業承継における資金面でのハードルを低くする効果的な手段となり得ます。
事業承継を考える際、経営者は保有する自社株式を後継者に引き継ぎたいと考えるのが基本です。しかし、後継者がその株式を取得するための資金を十分に保有していないケースが多々あります。そこで、自己株式取得によって、現経営者が所有する株式を会社が一度買い取る方法を採用することがあります。
この方法では、会社が買い戻した株式には議決権がないため、現経営者が唯一の株主であれば、後継者は議決権の過半数を持つために、少ない株式の取得で済みます。後継者の株式取得の負担を軽減しながら、経営権のスムーズな移行が可能となるのです。
株主側(売却側)のメリット
続いて、株主側(売却側)における自己株式取得の主なメリットを解説します。
株式の現金化
非上場企業の株主にとって、株式の現金化は重要な課題です。上場企業の株式は市場で容易に売買できますが、非上場企業の株式は市場で取引されないため、現金化が容易ではありません。そこで、自己株式取得は非上場企業の株主が保有する株式を現金に換えるための重要な方法となります。
自己株式取得によって株式を売却することで、株主はその資産を現金化できます。これにより、株式という流動性の低い資産を流動性の高い現金に変えることができ、株主の資産運用の自由度が向上します。
特に経営者や創業者など、長期間にわたって株式を保有してきた株主にとって、自己株式取得は退職後の生活資金やその他のライフイベント(教育費や住宅購入など)に対応するための資金を確保する手段となります。
また、相続が発生した際、非上場企業の株式は相続税評価額が高くなることがあります。そこで自己株式取得を利用して株式を現金化することで、相続税の納税資金を確保しやすくなります。
非上場企業における自己株式取得のデメリット
自己株式取得は、株主価値の向上や資本構成の最適化など多くのメリットがありますが、一方でデメリットやリスクも存在します。非上場企業が自己株式取得を検討する際には、これらのデメリットを十分に理解し、慎重に判断する必要があります。
非上場企業側(買収側)のデメリット
非上場企業側(買収側)における自己株式取得の代表的なデメリットを4つピックアップし、順番に解説します。
資金繰りの悪化
非上場企業が自己株式取得を行う場合、多額の資金を必要とするため、企業の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
自己株式取得のための資金調達方法には、内部留保の取り崩しや新たな借入があります。
内部留保を取り崩して自己株式取得を行う場合、追加の借入を避けられます。しかし、内部留保を減少させることで、将来の投資機会や予期せぬ経済状況の変動に対する対応力が弱まる可能性があります。
これに対して、自己株式取得の資金を借入で賄う場合、企業は内部留保を維持できますが、借入金が増加し、利息負担が発生します。これにより、企業の財務リスクが増大し、資金繰りが悪化するリスクがあります。
自己株式取得により資金繰りが悪化すると、日常業務に必要な資金が不足し、企業の運営に支障をきたす可能性があります。これにより、仕入れや給与支払いなどの経営活動が円滑に進まなくなるリスクがあります。
成長投資の機会損失
企業が成長し続けるためには、設備投資、新規事業開発、研究開発(R&D)などへの継続的な投資が欠かせません。これらの投資は企業の競争力を高めるために重要な要素です。
自己株式取得に多額の資金を投じると、設備の更新や拡充に必要な投資が後回しにされる可能性があります。これにより、最新の設備を導入できず、企業の生産性や競争力が低下するリスクがあります。
株主側(売却側)のデメリット
自己株式取得が行われた際に、株主が納税しなければならない場合があります。これを「みなし配当」と言います。
みなし配当とは、株主が実際に配当金を受け取っていないにもかかわらず、自己株式取得によって株主に利益が分配されたとみなされることで課税される仕組みです。みなし配当の額は、株主が受け取った売却代金から、その株式に対応する資本金を差し引いた金額で計算されます。
計算式は以下のとおりです。
- みなし配当の額=売却代金-売却株式に対応する資本金等の額
ここからは、みなし配当について理解しやすくするため、以下のケースを例に説明します。
- 個人株主Aが500万円で保有していたB社の株式を、B社が1,000万円で自己株式取得した。A以外に株主はおらず、自己株式取得時点の売却株式に対応するB社の資本金等の額は700万円だとする。
この場合、Aが取得時に支払った500万円と自己株式取得価格1,000万円との差額である200万円が譲渡所得となります。また、売却価格の1,000万円と資本金額700万円の差額300万円がみなし配当として扱われ、配当所得として総合課税の対象となります。
なお、相続発生時に相続人が納税資金を捻出するために、相続した非上場株式を発行会社に買い取ってもらうケースもあります。この場合、一定の要件を満たせば、みなし配当に該当する金額を含む全額が譲渡所得として扱われる特例があります。これにより、総合課税の対象となった場合よりも低い税率が適用される可能性があります。
非上場企業における自己株式取得のルール・措置
非上場企業が自己株式取得を行う際には、法的な規制や内部手続きなど、いくつかのルールを遵守する必要があります。
非上場企業が自己株式取得を実施するにあたって知っておくべき主なルール・措置を紹介します。
会社法第155条が定めるルール
会社法第155条は、自己株式取得の基本的なルールを定めた条文です。企業が自己株式取得を行う際の条件や手続きを規定しています。
会社法第155条において、自己株式取得ができる場合は以下のとおり定められています。
| 自己株式取得ができる場合 | 補足 |
| 株主との合意による自己株式取得(会社法155条3号) | 株主との合意による取得は、自己株式の基本的な取得方法です。特定の株主から取得する場合も、全株主に対して行う場合も含まれます。 |
| 種類株式の効果としての自己株式取得(同法155条1号、4号、5号) | 取得条項付株式や取得請求権付株式のような場合、種類株式の効果として自己株式の取得が予定されています。要件を満たすと、種類株式の効果として自己株式取得を行うことが可能です。 |
| 非公開会社における自己株式取得(会社法155条2号、6号) | 非公開会社では、譲渡承認請求が不承認となった場合や、定款で会社の相続人に対する売渡請求が定められている場合、自己株式の取得が可能です。非公開会社では株主間の信頼関係が重要であり、このような閉鎖性を維持するために自己株式取得が認められています。 |
| 株式の整理に伴う自己株式取得(会社法155条7号~9号) | 単元未満株式や所在不明株主の株式など、株式の整理が必要な場合に自己株式の取得が認められています。 |
| 組織再編に伴う自己株式取得(会社法155条10号~12号) | 合併などの組織再編に伴い、例えば合併消滅会社が合併存続会社の株式を保有している場合、合併により合併存続会社が自己株式を取得することになります。このように組織再編に伴って自動的に生じる自己株式取得が認められています。 |
| その他 | 会社法施行規則27条により、上記以外にも特定の場合には自己株式の取得が可能とされています。 |
会社法第461条が定めるルール
会社法第461条は、自己株式取得に関する財源規制を定めた条文です。
自己株式の取得には、債権者の利益を守るための財源規制が設けられています。財源規制とは、企業が自己株式を買い戻す際、その支払い額が分配可能額(資本剰余金、利益剰余金の額)を超えてはならないというものです。
企業は減資手続きを通じて分配可能額を増やすことができます。減資手続とは、資本金や資本準備金から資本剰余金に資金を移すことです。ただし、この手続きを行う際には、債権者の利益を保護するために、異議申し立ての受付を通知する必要があります。
株式の譲渡損益に対する課税の繰延措置
2018年の税制改正により、企業が自己株式を対価として買収を行う場合、譲渡する株主は株式譲渡の損益に対する課税を繰り延べられるようになりました。
欧米では自社株を対価とするM&Aは一般的ですが、日本ではまだ普及していません。政府はこの制度を導入することで、日本でも自社株を利用した事業再編を促進しようとしています。
譲渡株主が株式譲渡の際に負担する課税を繰り延べることにより、売却の意欲を高め、M&Aの活性化を目指す措置です。
非上場企業における自己株式取得の注意点
非上場企業で自己株式取得を行う際に留意しておくべき点を2つピックアップし、順番に解説します。
自己株式取得実施後の株主構成を想定しておく
非上場企業が自己株式取得を実施する際には、その後の株主構成の変化を十分に考慮することが重要です。自己株式取得によって株主構成が大きく変わることで、経営権の集中や支配権の変動が生じる可能性があります。場合によっては、企業の意思決定や経営方針に影響が及ぶこともあるでしょう。
自己株式取得を行う際には、株主間のバランスを考慮することが重要です。特定の株主に経営権が集中しすぎないようにすることで、経営の安定化を図れます。具体的には、公正な意思決定が可能となり、企業の健全な成長が促進されるでしょう。
自己株式取得後の支配権の変動リスクを回避するためには、事前に株主構成の変化をシミュレーションし、支配権が分散するような対策を講じることが重要です。これにより、企業が予期せぬ経営権の変動に直面するリスクを軽減できます。
自己株式取得実施時の買取価格を適切に設定する
非上場企業が自己株式取得を実施する際、買取価格の設定は非常に重要です。適正な価格を設定することで、株主全体の公平性を保ったり、課税上の弊害の発生を防いだりできます。
非上場企業の場合、市場での取引価格がないため、財産評価基本通達に基づいた評価方法を用いる必要があります。
具体的には、同族株主の場合、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の2つの方法で評価額を算出します。一方、同族株主以外の株主の場合は、「配当還元方式」に基づいて買取価格を設定することが基本となります。
同族株主からの株式買取の場合、標準的な評価額ではなく特例的な評価額を設定することも可能です。しかし、買取価格が適正時価よりも高い場合や低い場合には、みなし配当やみなし贈与として課税されるリスクがあるため、注意が必要です。
買取価格は、売主や買主の状況など様々な条件を考慮し、メリットとデメリットを検討した上で決定する必要があります。M&Aや相続対策など、目的に応じて株価の算定方法も異なるため、正確なシミュレーションが求められます。公平で課税上の問題が生じない価格設定は非常に難しいため、専門家に相談することが推奨されます。
非上場企業における自己株式取得の方法・手続き
非上場企業における自己株式取得の方法は、主に以下の3つのケースが存在します。
- 株主を特定せずに取得するケース
- 特定の株主から取得するケース
- 子会社から取得するケース
それぞれのケースで必要な手続きを順番に解説します。
株主を特定せずに取得する場合の手続き
株主を特定せずに取得するケースでは、以下の流れで手続きを進めなければなりません。
①株主総会における普通決議
全ての株主から会社が自社の株を買い戻す際には、株主総会での普通決議で全員の同意を得る必要があります。特定の株主だけから株を買い戻す場合とは異なり、全員に平等に扱われるため、普通決議での承認が求められます。
②株式の取得価額・取得期間などの決定
会社が自社の株を買い戻すときには、その価格や期間を株主総会で決める必要があります。上場企業の場合、市場価格があるため価格の設定は簡単ですが、非上場企業では慎重に価格を決める必要があります。通常、株は適正価格よりも高い金額で買い戻されることが多いです。
③希望する株主による株式譲渡の申し込み
自社株の買い取りに賛成し、株式を売りたい株主は会社に対して株の売却を申し出ます。上場企業の株式は自由に売買できますが、非上場企業では、株式の譲渡には制限があり、所定の手続きを踏む必要があります。
特定の株主から取得する場合の手続き
特定の株主から取得するケースでは、以下の流れで手続きを進める必要があります。
①「売主追加請求」の権利を通知
特定の株主から自社株を買い取る場合、他の株主との間に不公平が生じることがあります。このため、他の株主は「売主追加請求」を行って、自分の持ち株も買い取ってもらうことができます。企業は、この権利があることを株主に知らせる必要がありますが、株主総会で売主追加請求が否決された場合には、手続きを進めることはできません。
②株主総会における特別決議
特定の株主から自社株を買い取るには、株主総会での特別決議が必要です。これは、全ての株主から株を買い取る場合よりも株主への影響が大きいためです。株主総会では、自社株の買い取りを承認するだけでなく、取得する株数や価格、期間なども決定します。
③取締役会における決議・決定
株主総会で自社株の買い取りが承認された後、取締役会で具体的な手続きを決めます。取締役会で決定した内容は、株主に通知しなければなりません。
④株主に対する通知・公告
企業は、株主総会や取締役会で決定した株数、価格、期間などの情報を株主に通知する必要があります。上場企業の場合、これらの情報を官報や電子公告で知らせることもあります。
⑤希望する株主による株式譲渡の申し込み
特定の株主以外の株主も、自分の株を売りたい場合は「売り主追加請求」を行います。ただし、この請求が認められない場合もあるため、事前によく確認することが重要です。
子会社から取得する場合の手続き
子会社から自社株を買い戻す場合、株主総会を開く必要はありません。これは、子会社からの株式取得が株主に大きな影響を与えないと考えられているためです。このようなケースでは、取締役会での承認を得ることで自社株を買い戻すことができます。
非上場企業における自己株式取得のルールまとめ
非上場企業における自己株式取得は、企業の資本構成や株主構成に大きな影響を与えるため、慎重に実施しなければなりません。自己株式取得の手続きや法的要件、財務への影響など、考慮すべき要素が多岐にわたるため、適切に進めるためには高度な知識と経験が必要です。
非上場企業における自己株式取得について不安があれば、企業法務に詳しい弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は会社法や関連する法令について専門的な知識を持っており、企業が自己株式取得を行う際に必要な手続きを適切に進めるためのアドバイスを提供します。これにより、法令遵守を確保し、法的リスクを回避できます。