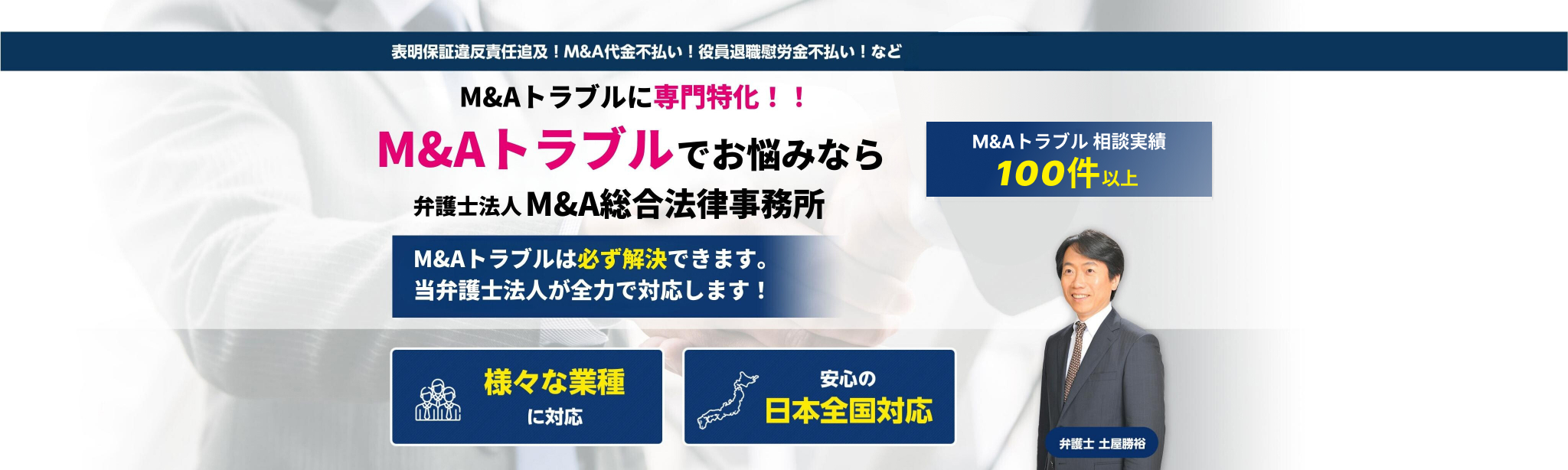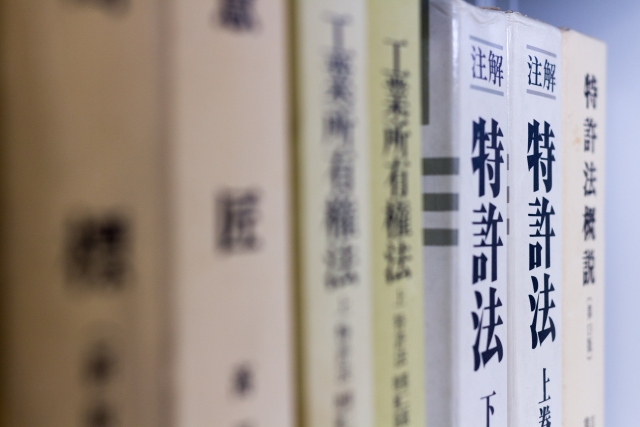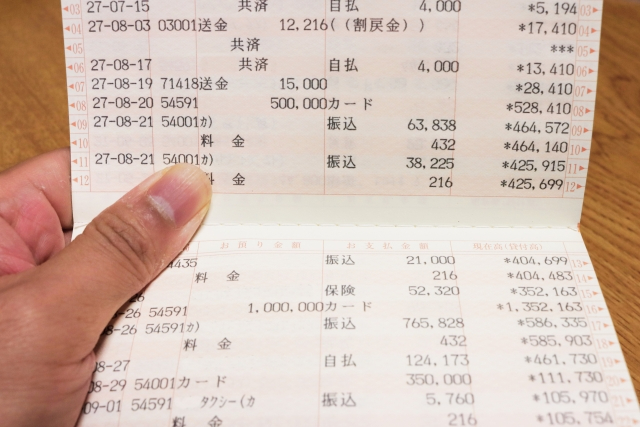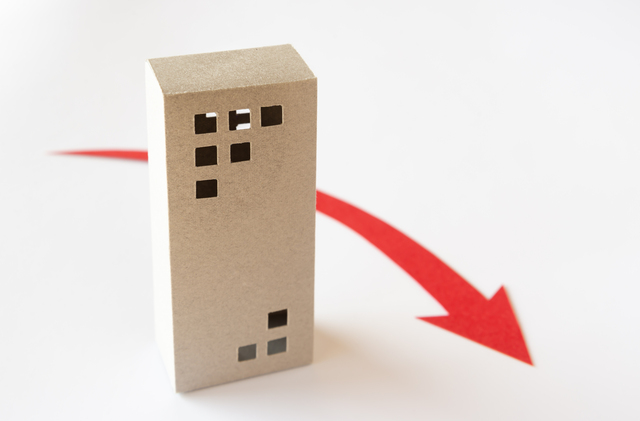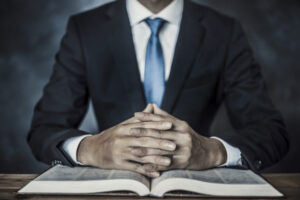M&Aトラブルの類型及び現状!

近時、中小企業のM&AにおいてM&Aトラブルが増加しており、M&A総合法律事務所に対してM&Aトラブルに関するお問い合わせも増加しています。
これは、近時における事業承継M&Aの増加や多くのプレイヤーがM&Aビジネスに参入していることや、M&Aマーケットの拡大に伴い、経験の浅い買主がM&Aに参入していること、その結果として、M&Aの失敗が増加していることなどが理由であると思われます。
M&Aは財務・会計・税務・法務の総合格闘技と言われるほど、さまざまな専門的知識と広範な知識、かつ多様な経験が必要となります。M&Aの増加に伴い今後も、M&Aの失敗やM&Aトラブルは増加し続けるものと思われます。
当事務所がM&A業務を開始した10年以上前の時期は、M&Aトラブルに関する裁判例というものはほとんど存在しなかったのですが、近時はM&Aトラブルに関する裁判例が、ニュース、報道や法律雑誌を賑わしています。
弁護士法人M&A総合法律事務所にも弁護士業界関係者を中心に、M&Aトラブルに関するセミナーの開催や執筆の依頼が多く寄せられているところです。
また、M&Aの当事者だけの問題ではなく、M&AアドバイザーやM&A仲介会社がM&Aトラブルに巻き込まれることも多くなっています。
この記事では、弁護士法人M&A総合法律事務所において実際に相談を受けたり実際に経験・対応したM&Aトラブルについて、まとめています。
M&A当事者やM&Aアドバイザーが、これらのM&Aトラブルに巻き込まれないためにはどうしたらよいか、このようなM&Aトラブルに巻き込まれた場合どうすればよいかについて検討し、これによって、M&A当事者やM&Aアドバイザーが今後幅広く、事業承継M&Aに取り組むことができれば、弁護士法人M&A総合法律事務所としても非常に幸いです。
M&Aトラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所 | M&Aトラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所
M&Aトラブルなら弁護士法人M&A総合法律事務所
M&Aにおける名義株主トラブル
まずは、名義株主トラブルです。
平成2年商法改正以前は、株式会社設立のため7名の株主が必要であったこともあり、また、取引先や金融機関などとの関係、又は法令など(金融商品取引法や開示規制や欠格事由に該当する株主や外国人持株規制など)の関係で、名前を表に出せない又は出したくない株主がいる場合、いわゆる名義株主の問題が生じます。
名義株主は、実質株主が他人の名義を借りて株式会社の株主になった場合に生じます。また、従前、多数の株主が存在していた場合であっても、オーナー経営者が、会社管理の煩雑さから勝手に株主名簿を書き換え、株主の名義を自分に集約させて名義株主となっているケースも多くあります。
判例上、出資金の拠出者である実質株主が株主権を有するものとされ、名義株主は実質株主の意向に反して株主権を行使してはならないものとされています。
M&Aが行われた場合、株式譲渡代金は名義株主が取得してしまいますが、実質株主や真実の株主には、自分の株式に相当する株式譲渡代金を受け取る権利があります
M&Aが行われたことを知った実質株主や真実の株主が、売主に対して訴訟を提起し損害賠償請求をした事例や、対象会社に対して、株主の地位の確認を求めた事例もまま存在します。
そのような事例において、多くのケースでは、名義株主覚書(名義株主に実質株主の指示に基づき株主権を行使することや名義書換請求を行うことを義務付ける覚書)が締結されていることはそれほど多くはないものの、その株主が、真実、出資金を拠出した実質株主であるか否か、真実の株主であるのか否かが問題となることが多く、実質株主や真実の株主がそれを証明できた場合、名義株主や対象会社は、その株主を株主と認め、損害賠償をすることが必要になります。
なお、この株主権については時効にかかることはないため、何らかの対応をしない限り永久に問題が解消することはなく、実質株主や真実の株主としては、いつまでたっても、名義株主や対象会社に対して損害賠償請求を行うことができるのです。
他方、少数株主は、知らない間に自分の株を売却されてしまい、名義株主に株式を握られていることもあります。
この場合は、実質株主や真実の株主として、ご自身が出資金を拠出した証拠(例えば預金通帳など)はないか、銀行から取り寄せることはできないか証拠集めをして、泣き寝入りする前に、会社に対して株式を高値で売却することを志向することとなります。
M&Aにおける敵対的少数株主トラブル
次に、敵対的少数株主トラブルです。
事業承継M&Aの対象となる会社は、戦後から高度経済成長期にかけての昭和の年代に創業されており、すでに、一代や二代、相続が発生していることも多くなっています。
当初は、創業者1名で創業したにも拘らず、創業者が亡くなり、ご子息3-4人兄弟が事業承継し、現在においては、そのご子息である孫の代が経営していることも多いのです。
そして、対象会社は3-4つのファミリーが経営権を争い、株主が2-30人いる等、株主関係が非常に複雑になっていることもあります。
このような場合、いざM&Aを行おうとすると、困難が立ちはだかるのです。
M&Aの買主としては、対象会社の経営に対する支配権を確立したいため、株式の100%の買収を希望することが多くなっています。したがって、M&Aにおいて、敵対的少数株主が存在するような対象会社を買収したいとする買主候補は、なかなか出現しません。
そこで、売主としては、事業承継M&Aの買主候補会社が出現するようにするため、敵対的少数株主から株式を買い集めることが必要となるのです。
少数株主が親しい親族や関係者であれば、オーナー経営者が話しさえすればその保有する株式を売却してくれることもあると思われます。
しかし、少数株主からの株式の買い取りは相対交渉となるため、必ずしもスムーズには進まず、また、少数株主に事業承継M&Aの話が存在することを察知された場合、少数株主から足元を見られて高い金額を吹っ掛けられることもあるのです。
また、オーナー経営者としては、そのような敵対的少数株主については、スクイーズアウト(少数株主排除)の方法で、株式を強制買取する方法もあるのですが、この場合、いずれも、反対株主には株式買取請求権が与えられるため、株式買取価格決定申立を提起され、裁判に巻き込まれる可能性が高いのです。
他方、社長から、株式の買い取りの申し出が来ている会社であれば、その会社はM&Aの準備をしている可能性が高く、長年塩漬けにされていた株式が適正価格以上で売却できる可能性があることから、少数株主としては、その時は、タイミングを逃さずに高値での株式売却を志向することとなります。
M&Aにおける従業員問題
M&Aを行った場合、対象会社のオーナーが変更になるのであり、従業員としては、旧オーナーがいなくなることで対象会社に対する忠誠心や業務に対するモラルが低下することが多く、M&A後に退職する従業員も増加し、対象会社の事業の運営がスムーズに進まなくなることもあります。また、M&A後に、重要な従業員が必ずしも買主の言うことを聞かず、M&A後、対象会社の業績が悪化することもあります。
また、労働法制は非常に広範かつ複雑であり、かつ裁判例も多々存在することから、中小企業においては従業員の管理を完璧に行うことができていないことも少なくなく、未払残業代が存在することもあります。
そのような会社において、M&A後、従業員が、対象会社を退職し、対象会社に対して未払残業代を請求してくることが非常に多くなっています。
M&Aトラブル事例:M&A買収した会社が従業員に対する未払給与を抱えていた場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら M&A買収した対象会社が従業員に対する未払給与を抱えていた場合 M&A買…
M&AにおけるCOC条項トラブル(チェンジ・オブ・コントロール条項トラブル)
対象会社の取引契約や賃貸借契約には、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)が規定されており、対象会社の株主や代表取締役が変更になるなどの対象会社の支配権が移動となる場合、取引先や賃貸人の事前承諾や事後届出が必要とされることが多く、特に、事前承諾を得ずにM&Aを実行し、対象会社の株主や代表取締役が変更になった場合、それがその取引契約や賃貸借契約の解除原因となることが多くなっています。
取引契約や賃貸借契約が実際に解除されてしまったら、対象事業の事業価値を著しく毀損する可能性があり、また、実際に解除されなかったとしても、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項(COC条項)に基づく解除権を背景に、取引先や賃貸人から多額の契約更新料を要求されたり、多額の保証金の差し入れを求められたり、これを契機に、取引条件や賃料の変更(取引条件の悪化や賃料の増額)を要求されることもあります。
M&Aにおける表明保証条項違反トラブル
M&Aトラブルの中では、この表明保証に関連するM&Aトラブルが最も多いというのが印象です。
表明保証とは、株式譲渡契約書などのM&A契約書に規定される主要な条項であり、M&Aの当事者が相手方に対して、一定の事項が真実であり正確であることを表明し、表明したことを保証する条項です。
M&Aに際しては、買主は、対象会社に対してデューデリジェンス(DD)を行うものの、デューデリジェンス(DD)による対象会社の事実関係の調査・把握には限界があり、必ずしも全てのリスクが明らかになるわけではありません。
特に、事業承継M&Aの対象会社である中小企業・零細企業では、十分な管理がなされていないことも多く、十分なデューデリジェンス(DD)が困難であることから、買主としては、売主に表明保証をさせることにより、想定しないリスクが存在しないことを確約されることとなります。
そして、売主としては、表明保証に明示された事項については、それが虚偽であった場合は、契約書上、売主の損害賠償責任・補償責任が発生することになり、結果として、買主が想定しないリスクを回避することができるのです。
そうであるからこそ、表明保証条項違反が存在した場合、買主としては、満を持して表明保証条項違反による補償請求・損害賠償請求を行うのであり、M&Aトラブルが発生するのです。
例えば、対象会社の従業員に未払残業代が存在しないとの表明保証は存在していないでしょうか。労働法制は非常に広範にわたり、かつ裁判例も多々存在することから、中小企業においては従業員の管理を完璧に行うことができていないことが多く、未払残業代が存在している可能性が高いです。
また、M&Aが完了した場合、対象会社のオーナーが変更になるのであり、従業員としては、旧オーナーがいなくなることで対象会社に対する忠誠心や業務に対するモラルが低下することが多く、退職する従業員も増加し、それを契機に、対象会社に対して未払残業代の請求が行われることが多くなっています。
対象会社に未払残業代の請求がなされ、対象会社がその従業員に対して未払残業代を支払うと、その次は、買主としては、対象会社や旧オーナーに対して、満を持して表明保証条項違反による補償請求・損害賠償請求を行うこととなります。M&Aトラブルの連鎖です。
これが未払残業代ならまだよいのですが、
- 従業員が退職し、重要取引先を持って逃げた。
- 販売したソフトウェアにバグがあることが判明した。
- 重要店舗の賃貸人から賃貸借契約を解除された、更新料を請求された、賃料を値上げされてしまった。
- 金融機関から政策融資の返済を求められた。
- 対象会社の保有する在庫の多くが陳腐化した不良在庫であった。
- 想定外の多額の前受金が存在した。
- 対象会社の重要な工場設備が故障しており、その補修には多額の費用が掛かる。
- 対象会社の決算書には過去既に回収してしまった多額の売掛金が引き続き計上されたままだった。
- 対象会社の決算書に多額の仕入額が計上されていない。
このような対象会社の企業価値に重大な悪影響を及ぼす表明保証条項違反があった場合は、M&Aトラブルも大きくなってしまいます。
買主としては、このような表明保証条項違反が発見された場合、そのままでは多額の損失を被ってしまい、そのM&Aが失敗に終わってしまうため、否応なく、売主に対して、表明保証条項違反に基づく補償請求・損害賠償請求を行うこととなります。
実際のケースでは、買主が、旧オーナーに株式譲渡代金を一部でも返還するよう求める形になります。旧オーナーが、顧問として引き続き対象会社に出勤していた場合は、気まずくなり出勤できなくなります。ただ、旧オーナーにも、それなりの負い目があるのか、実際に、株式譲渡代金の一部を返還してしまうこともあります。
ただ、買主が、デューデリジェンスを怠ったことに問題があり、半面、旧オーナーは、何も聞かれなかったので特段言わなかっただけであり、言おうとしても言う機会を逃した程度であることも多く、買主の帰責性が大きい場合も多いと思われます。また、買主が被った多額の損失の多くは、買主が、M&A実行後に、対象会社の従業員や取引先を適切に手当てしなかったのが原因であることも少なくないのです。
また、平成18年1月17日の東京地方裁判所判決平成16年(ワ)第8241号(アルコ事件)では、表明保証条項違反につき、売主がデューデリジェンスに資料を開示していたことに関連して、買主が悪意又は重過失がある場合、表明保証条項違反に基づく補償請求・損害賠償請求が認められない可能性があることを判示しつつ、売主が表明保証条項違反の事実を故意に秘匿したとして、売主の表明保証条項違反の責任を認めています。
すなわち、売主が表明保証をしたとしても、買主が表明保証条項違反の事実を認識していたり、認識可能性があったのに重大な過失により認識していなかった場合には、買主は、売主に対して、表明保証条項違反の補償請求・損害賠償請求を行うことができないのです。
また、売主は、デューデリジェンスに資料を開示していたとしても、表明保証条項違反の事実を故意に秘匿した場合は、表明保証条項違反の責任を免れないのです。
ですので、会社から補償請求・損害賠償請求を行われそうになっている旧オーナーがいる場合、負い目を感じずに、冷静に状況を分析する必要があるかと思われます。
裁判が提起されそうになっても、安易に妥協するのではなく、冷静に状況を分析して対応する必要があります。
中小企業M&Aトラブルの原因と類型!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら 弁護士法人M&A総合法律事務所には、日々、M&Aトラブルに関する相談が寄…
M&Aトラブル事例:M&A買収した会社が不良債権を抱えていた場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら M&A買収した対象会社が不良債権を抱えていた場合 M&Aにより企業の買収…
M&Aにおける株式譲渡代金不払いトラブル・役員退職慰労金不払いトラブル
M&Aでは、株式譲渡の対価をめぐるトラブルも発生します。株式譲渡の対価について、
- 売主に対する株式譲渡代金を分割払いにする。
- 旧オーナーに対する退職慰労金を後払いにする。
- 当面、顧問料を支払う。
- 売主から担保提供をしてもらう。
- 株式譲渡代金を一定期間エスクロー口座に預かってもらう。
などの対応がなされることもあります。
M&Aが失敗した場合、買主側は、売主である旧オーナーに対して、表明保証条項違反を主張して損失を補償させようとしますが、その際、株式譲渡の対価について上記のような対応を取っている場合は、買主が納得できる結果を得られるまでは、売主に対するそれらの支払いを停止することもあります。
このような場合、売主としては、泣き寝入りするのではなく、表明保証条項違反トラブルと同様に冷静に状況を分析して対応する必要があります。
M&Aにおける役員の責任追及トラブル
前述のとおり、M&Aはたいてい失敗すると言われます。M&Aの買主は、M&Aの完了後、遅かれ早かれ、そのM&Aが失敗だったと気づくこととなると思われます。
M&Aの買主の社長は、実際にM&Aに失敗した場合、そのM&Aの失敗の原因は、自分の見通しの甘さや検討の不足などにあったとして反省するのではなく、その対象会社の旧オーナーである売主に責任があるとして責任転嫁する傾向があります。
M&Aでは買主も中小企業であることも多く、中小企業のワンマン経営者が、M&Aの失敗を自分のミスであると自認することは少ないのです。
会社を売却したオーナー社長で、M&Aの後、売却した対象会社から役員の責任を追及されている旧オーナー、又はそれを理由に、不当に役員や顧問を解任されてしまった旧オーナーの皆様は、買主の社長が自分の責任を旧オーナーに転嫁しようとしていることを理解して、泣き寝入りすることなく、冷静に状況を分析して対応して頂くことが良いと思います。
M&Aトラブル事例:M&Aで買収した会社が第三者の知的財産権を侵害していた場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら Contents M&Aと知的財産権侵害M&Aと知的財産権侵害と表明保証条項違反…
M&AにおけるM&A後の競業トラブル
買主は、事業承継M&Aに伴い、クロージングに際して、旧オーナー経営者から、事業運営に関するノウハウやネットワークの引き継ぎを受けます。
ただ、対象会社のノウハウと顧客との関係性を有する旧オーナー経営者が、対象会社と同じ事業を行う会社を立ち上げ、同じ事業を開始することがあります。旧オーナー経営者自身ではなくても旧オーナー経営者が関与しつつ、対象会社の元従業員などが、対象会社の取引先や下請先などと協働し、対象会社と同じような事業を開始することがあります。
事業承継M&Aの対象会社は中小企業・零細企業であり、その事業運営に関する主たるノウハウやネットワークは、オーナー経営者である売主個人に帰属していることが多くなっています。仮に、旧オーナー経営者が、事業承継M&Aのクロージング後、対象会社の事業と同じ事業を立ち上げた場合、対象会社の強力な競争相手となるのみならず、重要なノウハウやネットワークなどは旧オーナー経営者に帰属していることから、旧オーナー経営者が退任したそちらのほうに行ってしまうことも多いと思われます。
また、旧オーナー経営者が対象会社の事業と同じ事業を立ち上げた場合や立ち上げることを考えていた場合、買主は、旧オーナー経営者から、対象会社の事業運営について十分な引き継ぎを受けることは期待できず、対象会社の企業価値は大きく毀損し、買主の想定する株式譲渡価格の前提が崩れることとなります。
そこで、事業承継M&Aにおける株式譲渡契約書においては、旧オーナー経営者の競業避止義務を規定することが一般的となっています。
しかし、旧オーナー経営者の競業避止義務違反であるとして、旧オーナー経営者の責任を問えるかというと、必ずしも容易ではないのが実情です。すなわち、このような旧オーナー経営者の競業行為は、いろいろな形態で行われる可能性があるため、本来、競業避止義務としては、あらゆる場合を想定した規定を記載しておかなければいけなかったのです。
典型的には、競業行為をする者が、自ら又は会社を設立して、対象会社の事業と同じ事業を行うものの、そのような明らかな競業行為をする者は多くはいません。まず、競業行為をする者が、自ら前面に出て競業行為をするのではなく、他の者に競業行為をさせ裏から操ったり、ライバル企業を支援したり、対象会社の事業と全く同じ事業は行わないものの、非常に類似した事業を行うなど、さまざまな形で競業行為が行われます。やはり、旧オーナー経営者が競業行為を行う場合は、外部に協力者がいる場合が多く、それは、対象会社のライバル企業や取引先や下請け先などであることも多いのです。
そのような会社が、対象会社の収益性の高さに嫉妬し事業承継M&Aが行われた機会に、対象会社のノウハウやネットワークを流用し、対象会社の損失を厭わず、対象会社の事業と同じ事業を開始するのです。そのような場合、オーナー経営者としては、対象会社の事業の重要なノウハウや顧客情報などを持ち出し、また対象会社における重要な技術情報などを抹消し、対象会社の企業価値を積極的に毀損するとともに、ライバル企業に利益を供与するのです。オーナー経営者が対象会社を退職後、ライセンサーに転職し、ライセンス契約を解除して、対象会社の事業と同じ事業を開始することなどもあります。
そのような場合、旧オーナー経営者の競業避止義務違反であることを立証することが容易ではなく、なかなか法的手段を講じることができません。
ただ、買主側としては、粘り強く、かつ、泣き寝入りすることなく、旧オーナー経営者の競業避止義務違反に対応してゆく必要があります。
M&AにおけるM&A後の顧客の離反問題
M&Aが完了し、取引先との取引契約を承継したからといって、取引先との取引が、従前と同様の水準で継続できるとは限りません。
取引先は、常に有利な取引相手を探していますし、有利な取引相手を発見したらすぐに取引先を変更するものです。
特に旧オーナー経営者と関係の深い取引先の場合は注意が必要です。
旧オーナー経営者が、M&A後、自分で同じ事業を始めてしまい、対象会社の取引先が旧オーナーに取引先を変更し、対象会社との取引を取り止めてしまう可能性もあります。旧オーナー経営者でなくとも、対象会社の役員や従業員、その取引先の担当者などが、対象会社を退職し、同じ事業を始めて取引先を取って行ってしまうこともあるし、対象会社の役員や従業員などが取引先を同業他社に紹介してしまい、手数料を貰っていることもあります。
また、買主が、M&A後に速やかに取引先のフォローをしなかったため、将来の取引に懸念を感じた取引先が取引を取り止めてしまうこともあります。
特に重要な取引先が、このような事由で、対象会社と取引を取り止めてしまう場合、対象会社の企業価値を著しく害するものとして、買主としては大きな損害となってしまいます。
M&A詐欺トラブルに巻き込まれた場合はどうする?M&Aの買い手/売り手の詐欺の典型例から対処方法を紹介
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら 近時、M&Aがブームになっており、売主と買主の裾野が広がっているところで…
M&Aにおける粉飾決算問題
M&Aに際しては、買主は、対象会社に対して、デューデリジェンス(DD)を行うものの、デューデリジェンス(DD)による対象会社の事実関係の調査・把握には限界があり、必ずしも全てのリスクが明らかになることはありません。
対象会社の決算書についても、デューデリジェンス(DD)だけでは、粉飾決算は明らかにならないこともあります。
また、そもそも、中小企業の決算書に関する会計基準は比較的柔軟であり、大企業であれば粉飾決算と言える場合であっても、中小企業については粉飾決算とまでは言えないケースも多いです。
また、税務署としては、必ずしも会計基準に従った決算書でなくても、税金が不当に減額になるような決算でなければ、特段指摘することもありません。
例えば、中小企業において、退職給付債務が適切に計上されていないことは普通であるし、減価償却費も必ずしも計上されていないことも多く、また、資産価値の無くなった有価証券やゴルフ会員権もそのまま計上されていることも多くなっています。
不良在庫もそのまま計上されていたり、原材料の仕入れについても、必ずしも適時に計上されていなかったりします。また、不動産についても、バブルのころに購入したのであれば、大幅な含み損を抱えていると思われますし、戦後まもなく購入したのであれば大幅な含み益を抱えていると思われます。
中小企業については、決算書を見ているだけでは、その実態を把握することはできません。M&Aに慣れた公認会計士や税理士を指名して、事前に、対象会社の財務デューデリジェンスを実施するしかありません。
M&Aトラブル事例:M&A買収した会社が粉飾決算をしていたことが発覚した場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら Contents はじめに:M&Aにおける粉飾決算リスクの深刻な現実M&A買収に…
M&Aトラブル事例:M&A買収した対象会社の貸借対照表の利益が水増しされていた場合
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら Contents M&A買収した対象会社の貸借対照表の利益が水増し!M&A買収に…
M&A買収後のトラブル!事例から見る対策!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら M&Aで後継者不在の会社を買収して、経営者を変えたら、業績もアップして、…
M&AにおけるM&A後の経営不振問題
M&Aの後、対象会社の業績は落ち込むことが多くなっています。
売主としては、M&Aにおいて対象会社を少しでも高く売却したいため、M&Aの直前の年度においては、駆け込みで売上を上げ、仕入れを減らし、経費を節減し設備投資を減らし、従業員の給与を最大限絞るなどし決算書をきれいにし、最大限、企業価値を高めてからM&Aを実施することが多いのです。
旧オーナー経営者としては、対象会社を売却するに際して、従業員に特別ボーナスを出したり、特別昇給を確約したりすることも多くなっています。また、取引先に頼んで商品を押し込んだため、M&A直後は商品が全く売れないとか、設備投資を全くしていなかったため、M&A後において生産設備が陳腐化し、M&A後早々多額の修繕を行わなければならないことも多くなっています。
やはり、M&Aに際してM&Aに慣れた専門家を指名し、事前に対象会社のデューデリジェンス(DD)を綿密に行うことは必須と思われます。
M&Aトラブル事例:M&A買収した会社が経営悪化していることを説明しなかった場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら Contents M&A買収した対象会社が経営悪化していることを説明しなかった場合…
M&Aトラブル事例:M&Aで買収した会社の財務状況について虚偽の説明をされ実質的に破たん状態であった場合!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら Contents M&Aした会社が破綻状態M&Aではすべてを説明する必要はない!M…
M&AにおけるM&A仲介料トラブル
M&A仲介業者のM&A仲介料が高いとのことで、M&Aの当事者がM&A仲介業者のM&A仲介料の支払いを拒むトラブルは後を絶ちませんが、それは、経験の浅いM&A仲介業者が急増している今日においては、クライアントであるM&Aの当事者のM&A仲介業者のサービスに対する満足度も低下していることの表れとも思われます。
特に注目すべきなのは、M&Aの売主が、対象会社にM&A仲介料を支払わせることによるトラブルです。
M&Aでは、仲介業者は、売主と買主を仲介します。対象会社は商品に過ぎず、仲介業者との取引関係は生じません。M&A仲介料も売主と買主が負担すべきものです。
それにも関わらず、売主側が、売却対象となる対象会社においてM&A仲介業者と業務委託契約書を締結したために、対象会社がM&A仲介業者にM&A仲介料を支払うことになっていることがあります。
M&A仲介料は、一般的に売買価格の5%程度とされることが多いです。例えば、対象会社の株式譲渡価格が5億円の場合はM&A仲介料は2500万円であり、M&A仲介業者は、この2500万円を、売主及び買主の双方から貰うことになります。ところが、売主側は、売主ではなく対象会社が、このM&A仲介料を支払う形になっているわけです。
この場合、買主は自社でも2500万円のM&A仲介料を支払い、完全子会社となった対象会社でも2500万円のM&A仲介料を支払うこととなり、買主側から二重に資金が流出することになります。
このような場合、売主と買主の間で、この対象会社の支払ったM&A仲介料2500万円の負担を巡って、トラブルが発生します。
また、対象会社とM&A仲介業者が業務委託契約を締結することにより、売主とM&A仲介業者との間に契約関係が発生しないため、売主からM&A仲介業者のコントロールができなくなるという問題があります。
この場合、売主がM&A仲介業者に不満があったとしても、M&A仲介業者に対して損害賠償請求などできなくなってしまうし、M&A後のM&AトラブルにおいてM&A仲介業者の協力を得られなくなってしまいます。
このようにM&A仲介業者との契約では、売主側の当事者が対象会社となっていることによるトラブルが多発しているため、注意が必要です。
M&A仲介の罠!事業承継直後の倒産や相次ぐトラブルの実態
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら 中小企業のM&A仲介は、国が積極的に推進しています。多くの仲介業者が業績を伸…
M&A仲介業者とのトラブル!M&A仲介業者は本当に売主の味方なのか?
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら M&A仲介会社は、本当に売主の味方なのか?敵なのではないのか?買主の味方…
まとめ
M&Aトラブルの類型及び現状について解説しました。
M&Aトラブルはこの記事で取り上げたものの他にも、たくさんありますし、トラブルの内容も事例ごとに大きく異なります。
M&Aトラブルに巻き込まれた場合は、当事者同士で解決しようとするのではなく、早めに弁護士に相談することが最善の解決策です。
今、まさにお困りの状況で解決策を探している方は、弁護士法人M&A総合法律事務所へご相談ください。
M&A買主によくあるトラブルとは?最新事例を弁護士が解説!
M&Aトラブルにお困りではありませんか? 電話: 03-6435-8418 ご相談フォームはこちら M&Aは弁護士のサポートにより、平和に終わることも少なくありません。しか…